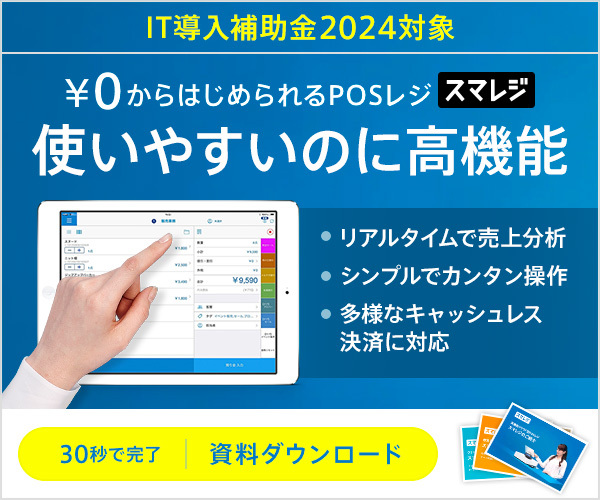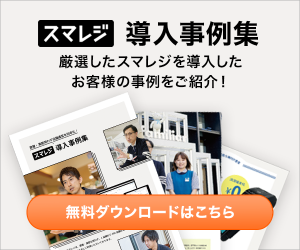about
「お店ラジオ」は、店舗経営にまつわるトークラジオ番組です。小売店や飲食店など各業界で活躍するゲストをお招きし、インタビュー形式でお届けしています。この記事は、InterFMで毎週日曜日にお送りしている「お店ラジオ」で放送された内容を未公開放送分も含めて再編集したものです。
#23 大阪王将のコロナに負けないお店づくり
#24 失敗しない出店計画のコツは百軒のぞき
今回のゲストは、大人気チェーンである大阪王将を中心に展開する株式会社イートアンドホールティングスの代表取締役CEOの文野直樹さんです。父から受け継いだ大阪王将をここまで拡大させてきた秘密はなんなのか。
「飲食店のビジネスモデルはすでに崩壊している」と断言するその真意とはなにか。これから飲食店を出す人に向けてのアドバイスやこれからの経営戦略まで、かなり掘り下げた内容をお届けします。
第一回は大阪王将の創業から現在に至るまでの経緯についてご紹介します。
この記事の目次
全国的餃子チェーン「大阪王将」
大阪王将は、特に関西で勢いがある、全国展開の餃子チェーンです。中国・台湾・シンガポール・タイにも進出しています。紛らわしいですが餃子の王将とは業務提携をしているわけではなく、経営は完全に分離しています。まずは餃子の王将との関係を軸に、大阪王将の経緯を説明しようと思います。

大阪王将は餃子の王将から、のれん分けして生まれた
1967年、僕の母方の親戚である加藤朝雄さんが京都に餃子の王将をオープンしました。餃子の王将は大繁盛し、京都市内を中心に拡大していきます。そんな時、繊維業界に勤めていた父がオイルショックによる影響で職を失ったんです。なんとか稼がなければ、と焦る父の元に飛び込んできたのは「親戚に餃子屋を始めて景気のいいおっちゃんがいる」という情報でした。
そこから餃子の王将に飛び込んで半年間修行させてもらい、のれん分けという形で大阪にて父がスタートしたのが「大阪王将」というわけです。とは言っても、この時はまだ餃子の王将を名乗っていました。元々の餃子の王将が京都を中心に出店していたことから、こちらを通称「京都王将」とし、父が始めた方を通称「大阪王将」とすることで区別していたようです。
餃子の王将と大阪王将は、徐々に険悪な雰囲気に
こうして京都王将は京都を中心に、大阪王将は大阪を中心に拡大していくことになります。ちょうど高度経済成長期だったので、それぞれものすごい勢いで出店していきました。両者は出店地域をなんとなく棲み分けることで良好な関係を保っていました。
しかし拡大するにつれ、いざこざが目立つようになってきました。段々と不文律としての「京都王将は京都、大阪王将は大阪」が崩れてきていたのです。これによって関係が悪化していきます。さらに、すでにそのとき、大阪王将は「大阪王将」を名乗るようになっていたのですが、一部で「餃子の王将」として営業している店舗が残っていました。これに対して餃子の王将が裁判を起こしたのです。
社長就任。はじめの仕事はゴタゴタの整理
こんなときに呼ばれたのが、当時愛知の方で「東海王将」を経営していた僕です。業績がよかったことを買われたのか、25歳で大阪王将の社長に就任することになりました。

僕の社長としての初めての仕事は、餃子の王将と大阪王将のゴタゴタを整理していくことでした。親戚同士が争っているのは嫌ですし、世間で「骨肉の争いだ」と話題にされてしまっているのも辛かったので、話し合いの場を設けていきました。
結果的に裁判は和解という形で終結し、「京都王将は『餃子の王将』、大阪王将は『大阪王将』を正式な名前とする」ということになりました。そこからはなんの問題もなく、自由競争でやっています。
大阪王将は、餃子専門店だった
以上のような経緯がありますし名前も似ているので混同されやすいのですが、餃子の王将と大阪王将ではメニューや方針は異なります。餃子の王将はオープン当時から大衆中華だったのですが、大阪王将は餃子専門店でした。はじめの頃は様々なメニューを試していたそうなのですが、父は餃子の王将で半年間しか修行していなかったので、料理のスキルが不足していたのです。
しかし、その中でも唯一評判がよかった餃子に絞ってみたところ、これがヒットしました。「メニューは餃子とビールだけ」というのが当時は業態として珍しかったようです。そこから僕が大阪王将を継ぐまでは全て餃子専門店でした。だから、今でも「餃子は大阪王将の方がいいよね」と言っていただけることは多いです。

お店が小さい分、テイクアウトに力を入れる
店舗にも違いがあります。餃子の王将は国道沿いにファミリーレストランタイプの立派なお店を展開していたのですが、大阪王将は駅前商店街やオフィス街にこじんまりとしたお店を出していました。そして、お店が小さい分、他で利益を出そうという発想になり、テイクアウトを始めることになりました。これが結果的にすごく効率が良い商売になったのです。
成功している父を見て、昔の同僚が「私もやらせてほしい」という話を持ってくるようになってきたので、のれん分けをして店舗を増やしていきました。だから、30~40店舗くらいまでは、店長は父の出身である繊維業界の方ばかりでした。
独自のシステム「のれんチャイズ」
その店舗の増やし方ですが、その後に僕たちはのれんチャイズというオリジナルのシステムを作っています。一般的にのれん分けが長年お店で働いていた人が看板を借りて独立することで、フランチャイズはブランドからノウハウや看板をもらう代わりにロイヤリティとしてお金を払うシステムです。
この二つにはそれぞれ面倒な問題があります。まず、のれん分けでは店舗をたくさん増やしていくことは難しいです。ではフランチャイズはどうかというと、加盟店もロイヤリティを払い続けなくてはいけないし、こちらも管理のためにスーパーバイザーと呼ばれる人を派遣しなくてはいけないので、お互いコストが重くなってくるんです。
のれんチャイズはこの両方の厄介な部分を解消したシステムです。まずロイヤリティは取らず、看板使用料だけをいただきます。そして素人の方が始めても一年間で利益が出るよう、こちらでしっかりと指導をします。(出向の原価だけはいただきます)これはのれん分けそのものを買ってもらうイメージです。単純化されたノウハウだけを与えるのではなく、こちらで育成するところまでを請け負うのです。
あとは僕たちが工場で作ったものを買ってもらえばいいというわけです。しかしこれは強制ではなく、違うものを使ってもいいです。その場合は自己責任だ、ということにしてお互い気持ちよく商売ができる環境作りに努めています。こうして僕たちは、きちんと育成をすることと、良いものを工場で作って提供することに集中すればいい、ということになったのです。