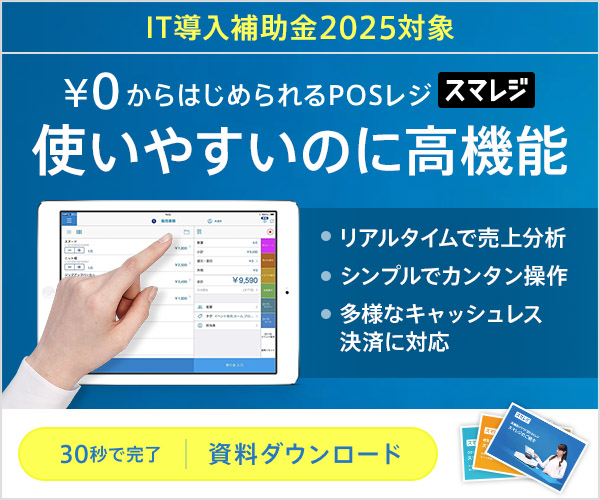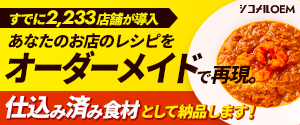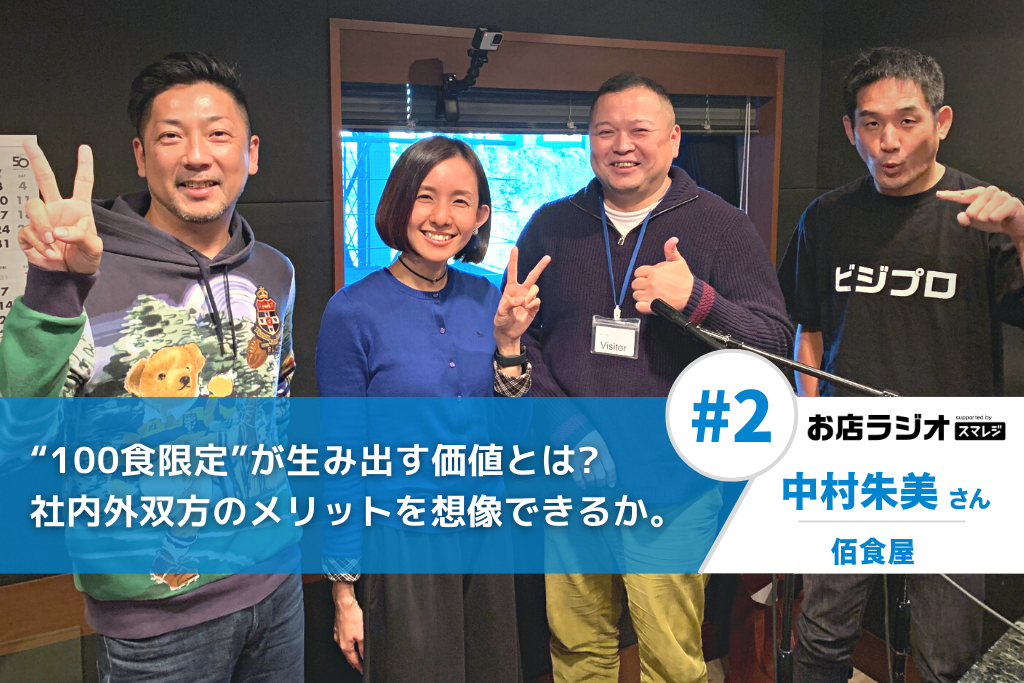about![]()
「お店ラジオ」は、店舗経営にまつわるトークラジオ番組です。小売店や飲食店など各業界で活躍するゲストをお招きし、インタビュー形式でお届けしています。この記事は、InterFMで毎週日曜日にお送りしている「お店ラジオ」で放送された内容を再編集したものです。
今回のゲストは、株式会社アイロム 代表取締役社長兼CEOの森山佳和さんです。ダイニングバー「ビーエイト」や魚料理専門の「サカナバル」を展開。また、缶詰工場の運営にも取り組むなど、飲食業界で独自の挑戦を続けています。森山さんの手がける事業の背景やこだわりについて伺います。
魚をテーマにした新業態の開発からスタートし、飲食店『サカナバル』を展開するに至った背景、恵比寿や六本木といった多様なエリアで成功を収めた戦略、さらに仕入れや経営の改善を通じて競争の少ない市場を構築した取り組みについて、3回に分けてお送りします。
第1回は、「サカナバル」誕生の背景や競争の少ない市場戦略、そして六本木への店舗拡大などについてお送りしました。
第2回は、立地条件やマーケティング手法、広告やSNSを活用した集客戦略、そして週末、年末の経営戦略などについてお送りしました。
第3回は、仕入れ改革と魚料理の可能性、そして大きな分母とコアファンの獲得などについてお送りします。
この記事の目次
仕入れ方法の変更により減価率55%から改善
「サカナバル」では、新鮮で良い魚を仕入れる仕組みをどう作るか、最初は本当に手探りでした。ビーエイトはローストビーフをメインにしていたため、魚の仕入れに関する知識も経験もなく、まずは築地市場に通うことから始めました。
当時は、魚を丸ごと仕入れ、自分たちで捌いてカルパッチョなどにして提供していましたが、うまくいきませんでした。次に、北海道や長崎などから魚を直送してもらう形に変更しましたが、これも失敗に終わりました。箱単位で仕入れた魚は2~3日以内に捌く必要がありましたが、ロスが大きすぎて原価率が55%に達し、全く利益が出ない状況だったのです。
ところが、「原価率55%」という話題がメディアに取り上げられ、一時的に注目を集めてしまったのですが、それは私たちのミスであったため、仕入れ方法を大きく見直す必要がありました。
そこで築地市場で加工してもらった魚を仕入れる形に変更することにしました。これで仕入れ原価は上がるものの、ロスが減り、調理が効率化されることで人件費の削減に繋がり、経営が軌道に乗り始めました。築地市場との取引を構築できたことで、魚の安定供給が可能となったのです。
加工品の仕入れ、産地直送の導入による仕入れの改善
魚を丸ごと買い、頭やアラを活用するのが商売の基本だと考え、アラ汁をお昼に提供していました。魚を丸ごと仕入れ、頭や骨をアラ汁に使っていたのですが、営業規模が拡大するにつれてアラの量が足りなくなってきました。また、100名規模のお客様へ対応する場合、魚の需要を予測するのが難しく、特定の魚が不足したり余ったりする非効率な状況が続きました。
肉であれば使える部位が多く保存も効きますが、魚は一匹あたりの可食部分が少なく、寿司屋のような小規模店舗ではうまく活用できても、私たちの規模では非効率な結果になってしまいます。そこで、築地市場で加工済みの魚を仕入れる方法に切り替え、課題に対応することにしました。
その後、現在も続けている産地直送を導入することになりました。仕入れ先の開拓は主に紹介によるものでしたが、「魚バルをやっている」と話すと多くの方が興味を持ってくださり、仕入れの提案をいただける機会が増えました。仕入れ先を選定する際のポイントは、送料と発注しやすい環境が整っているかどうかです。アナログな手続きや時間制約が多い場合、発注が難しくなります。例えば、夜中の1時まで働くスタッフがいるため、早朝に「今日の魚どうしますか?」と電話が来るような体制では継続が困難です。
魚の鮮度を保つため、ほぼ毎日仕入れる必要があるため、安定した取引が可能かどうかが、非常に重要になります。
魚の種類は無限にある
調理に関しては、魚をうまく捌き、鮮度を保ちながら提供する作業が求められ、高いスキルが必要になります。うちに来るスタッフには料理好きが多く、魚を捌けるようになりたいという意欲を持つ若い人や、独立を目指す人も多くいます。私たちのお店はコンセプトとして魚を中心に据えているだけで、それ以外は自由な発想で料理を作れる環境であり、スパニッシュやイタリアン、和食、中華など幅広いジャンルを扱うため、自分の力を試したい人には最適な場だと思います。
メニューは最初に私が案を作りますが、スタッフと調整しながら仕上げ、最終的には総料理長と共に完成させます。魚の四季や漁獲状況に大きく左右されるため、獲れない魚や価格変動に応じて柔軟に対応し、通年で同じメニューを出すのは難しいため、旬の魚を中心にメニューを変更しています。メニューには、粗利を重視するものと、利益は少なくてもお客様に喜んでいただけるものの2つのパターンがあります。前菜などでは、手間をかけながらも原価を抑える工夫をしていますが、どこでコストを抑えるかは常に難しい課題です。
また、すべてのメニューに魚を使っているため、バリエーションを考えることが重要だと思いますが、「魚ばかりで大変じゃないか?」とスタッフに尋ねたところ、「魚の種類は無限にある」という答えが返ってきました。肉と比べると、魚のバリエーションは圧倒的だというのです。マイナーで安価な魚でも、うまく調理すれば美味しくなり、利益を生み出せるというスタッフの考え方に、私は非常に感銘を受けました。
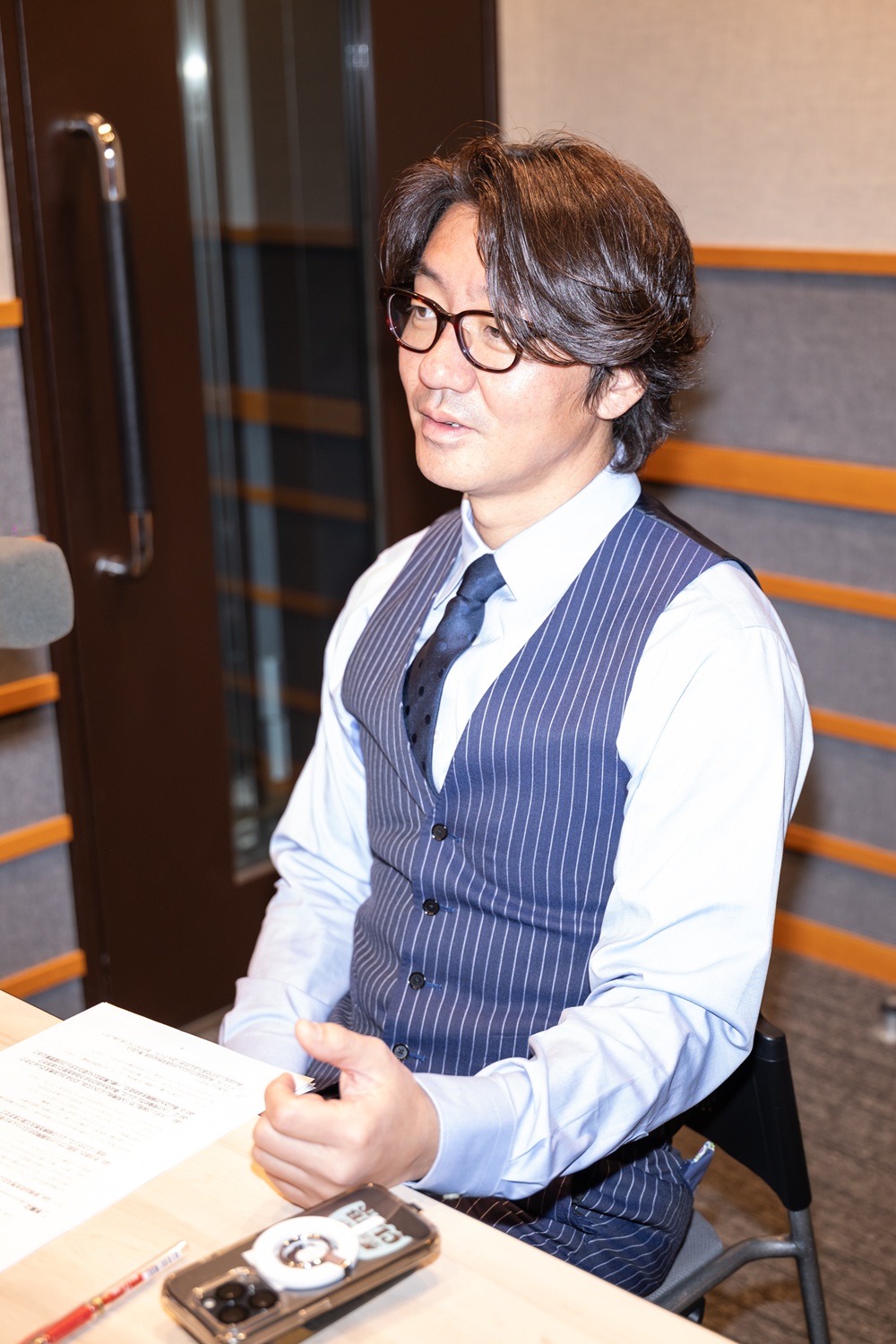
大きな分母の中からコアなファンを見つける
店舗拡大においてが、場所選びは非常に重要です。「サカナバル」が成功するかどうかは、経験的な直感で判断します。例えば、新宿では居酒屋や和食が主流で、魚バルのカタカナのイメージが客層に合わないと思う一方で、恵比寿や代官山、白金、目黒といったエリアは、ハイエンド層が住んでおり、「サカナバル」のニッチなコンセプトに適していると感じます。
「サカナバル」のようなニッチな業態では、大きな分母の中からコアなファンを見つけることができる場所が必要です。例えば、成城石井が出店しているようなエリアには、その可能性があるかもしれません。
また、店舗の規模としては、席数を減らして小規模にするという案も検討していますが、それでは売上規模が縮小してしまうため、利益をどう出すかが新たな課題となります。席数が多く、一定の売上が見込める形でないと効率的でないため、小規模な店舗を拡大する場合には、フランチャイズ(FC)の方が良いと考えています。
また、魚業態ではセントラルキッチンのようなモデルが十分に機能しづらく、築地や豊洲から各店舗へ魚を配送する際のコストが高く、ボリュームディスカウントが効きにくいため、効率化が課題となっています。豊洲の魚屋と契約し、セントラルキッチン的に運用する案も検討していますが、コスト削減には一定の規模が必要になります。今後、年間取引量を見込んだ契約が可能になれば、送料や仕入れコストを抑え、スケールメリットを活かすことができると考えています。
同じレシピでも味が変わる魚料理
メニューの原価はすべてリスト化して管理し、食材のグラム数を測定して正確に計算しています。現在、副材料、例えば乾物やオリーブオイルなどの価格が高騰していますが、これらも細かく原価に反映させています。
魚は日々の仕入れで価格が変動することが多く、同じ魚でも値段に差が出てしまうため、計算通りにいかない場合がありますので、メニューの変更は非常に早く、毎日調整することもあります。また、季節の食材を使ったメニューは2~3ヶ月で入れ替えるのが基本となっています。原価が上がったタイミングで即座に調整し、レシピや原価のデータを「カルテ」のように記録して管理しています。同じメニューを毎年繰り返すことはほとんどなく、基本的にはゼロから作り上げています。
料理にはトレンドがあるため、それに合わせてメニューを考え、毎年異なる内容を提供していますので、原価管理は非常に難しくなります。一物一価で取引される魚は、サイズや脂の乗り具合によって価格が変動するため、特にアクアパッツァのように丸ごとの魚を使う料理ではさらに難易度が上がります。脂の多い魚の場合、塩加減を調整しなければならず、その判断が料理の成否を左右するのです。
試食の段階では、細身の魚が美味しくても、脂が乗りすぎた魚で味が合わないこともありますし、同じ魚を使っても、隣席のお客様の料理と微妙に味が異なることがあるのです。これは、同じレシピを使用しても結果が変わってしまうのが、魚料理特有の難しさであり、同時に醍醐味でもあります。