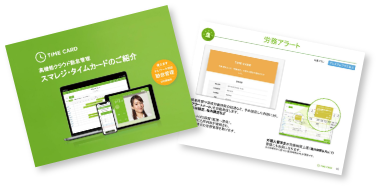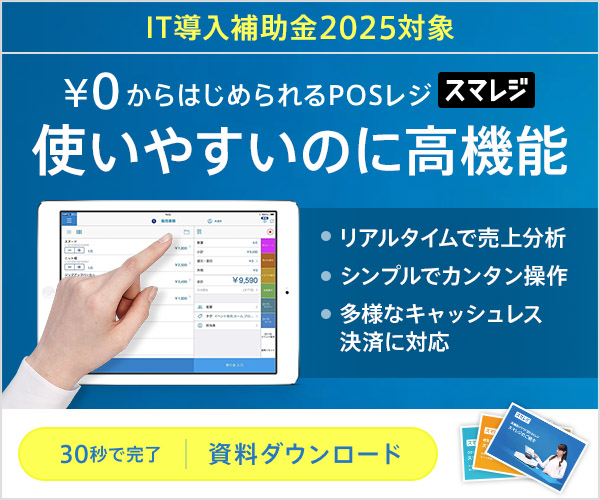勤務時間の管理方法はさまざまで、従業員とのトラブルを避けるためにも、厚生労働省の発行するガイドラインを把握することが重要です。
本記事では、勤務時間の管理方法や理解しておくべきガイドラインのポイントを紹介します。この記事を読んで、勤務時間を管理するときの参考にしてみてください。
この記事の目次
- 勤務時間とは?
- 勤務時間の管理方法には主に3つある
- 労働時間の把握や適切な管理も必要
- 法律は?労働時間に関するガイドラインのポイント
- 出退勤時間や労働時間の適切な管理には勤怠管理システムの導入がおすすめ
勤務時間とは?
勤務時間とは、始業時刻から終業時刻までのことをいいます。たとえば、午前9時に出社し、午後6時に退社したときの勤務時間は9時間です。勤務時間は企業によってさまざまで、5時間の短時間勤務もあれば12時間の長時間勤務もあります。
正社員で勤務時間が決められていれば、勤務時間は固定されています。しかし、アルバイトやパートの場合は、従業員や勤務日によって勤務時間が異なるケースが多いです。事業者が勤務時間を管理するには、従業員が何時から何時まで働いたのか把握しておく必要があります。
労働時間との違い
勤務時間に類似している言葉として、労働時間があります。労働時間とは実際に働いた時間のことで、始業時刻から終業時刻までの時間から休憩時間を引いています。労働基準法には、労働時間に応じて与えるべき休憩時間が以下のように定められています。
- 労働時間が6時間を超え8時間以下のとき:45分以上
- 労働時間が8時間を超えるとき:1時間以上
そのため、勤務時間によっては休憩時間を設けなければなりません。たとえば、午前9時出社の午後6時退社で勤務時間が9時間の場合、45分の休憩時間を設けると労働時間は8時間15分となり、労働基準法に違反しています。
上記の例の場合、事業者は休憩時間を1時間設けなければなりません。休憩時間の判断は、勤務時間から45分を差し引いて労働時間が8時間以下になるか、8時間を超えるかがポイントです。特にシフトを組むときは、休憩時間がバラバラになることが多いので、労働時間の管理は徹底する必要があります。
勤務時間の管理方法には主に3つある

勤務時間の管理方法はさまざまです。主な管理方法には、出勤簿、エクセル、タイムカードの3つがあります。それぞれのメリット・デメリットについて紹介するので、どの方法が自分に合っているかチェックしてみましょう。
出勤簿
出勤簿は、従業員自ら出勤時間と退勤時間を記録する管理表です。従業員が自分で記録するので、細かい時間を記録できる点がメリットといえます。一方で、従業員が記録した勤務時間を集計しなければなりません。
集計の手間がかかり、集計ミスによって給与計算ミスにも繋がる可能性があります。さらに、従業員が不正する可能性もあるため、記録が正確かどうか確かめるのは困難です。したがって、紙でも難なく管理できるほど従業員数が少ない事業者におすすめします。
エクセル
エクセルのソフトを使って、勤務時間を自動計算できます。事前に計算式を設定しておけば、出勤時間と退勤時間を入力するだけで瞬時に勤務時間の算出が可能です。パソコンさえあればわざわざ紙で用意する必要がないため、コスト削減にも繋がります。
しかし、関数を使って管理表を作らなければならないので、パソコンに慣れていない方は準備段階で苦労する可能性が高いです。また、入力ミスや不正の発生も考えられるので、事業者が小まめに管理表をチェックする必要があります。以上のことから、エクセルはパソコンを所有し、勤務管理のコストを抑えたい事業者におすすめです。
タイムカード
タイムカードは、専用の機械を使って用紙に出勤時間と退勤時間を打刻する方法です。出勤・退勤時に専用の紙を機械に通すだけなので、システムに疎い方でも簡単に利用できます。機械が打刻時間を記録するため、勤務時間の集計自動化の実現が可能です。
ただし、紙の場所さえ知っていれば第三者が打刻できるので、不正利用される可能性があります。また、打刻ミスをすると、データの消去や用紙の修正など手間がかかる点もデメリットです。
ちなみに、専用の機械と用紙を用意するのにコストが発生します。そのため、予算に余裕があり、打刻の習慣を取り入れたい方におすすめします。
勤怠管理システム
勤怠管理システムは、従業員の勤務状況をオンライン上で管理するシステムのことです。システムごとに用意された打刻方法で従業員の勤務時間を正確に管理し、給与計算など他システムと連携できます。
また、インターネット環境下であればどこでもアクセスできるため、リモートワークにも対応可能です。一方で、システムを導入するには、一定のコストがかかる場合があります。このことから、コストをかけてでも、業務効率アップやリモートワークの導入を図りたい方におすすめです。
労働時間の把握や適切な管理も必要

勤務時間だけでなく、労働時間の把握や適切な管理も必要です。ここでは、その理由について詳しく紹介します。
労働時間を管理しないとトラブルに繋がる可能性がある
労働時間の管理をしなければ、以下のようなトラブルに巻き込まれる可能性があります。
- 従業員が遅刻や早退したことを認めない
- 正確な残業代を支払えず、従業員からクレームがくる
- 労災の認定が下りない
労働時間を正確に管理できていなければ、たとえ従業員が1時間遅刻しても、言い逃れを許してしまいます。また、どのくらい残業したのか明確に記載されていなければ、適正な給与を払えず、最悪の場合、訴訟を起こされるかもしれません。
さらに、たとえば休日出勤中に事故に巻き込まれた場合、勤務管理表に出勤記録がなければ、労災が認定されないこともあります。労働時間は給与に直結するため、従業員と揉めやすい部分です。トラブルに巻き込まれると、不要なストレスを抱える可能性があるので、労働時間の管理は徹底しましょう。
法律は?労働時間に関するガイドラインのポイント

トラブルを避けるためにも、厚生労働省が公表したガイドラインをしっかり理解することが大切です。ここでは、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」をもとに、事業者の注意点をまとめました。労働時間に関する情報を押さえて、トラブルの発生を防ぎましょう。
使用者が労働者の始業と終業時間を確認・記録する
使用者(事業者)は労働者の始業と終業時間を確認・記録することが求められます。主な方法は、事業者自ら従業員の勤務状況を目視するか、タイムカードやICカード、パソコンの使用時間などの客観的な記録を確認することです。
ただし、これらの記録を鵜呑みにするのではなく、残業命令書や残業報告書など、使用者が労働者の労働時間を算出するための記録もあわせて参考にしましょう。
やむを得ず自己申告を行う場合は従業員に対する十分な対策を取る
従業員の労働時間の記録に自己申告制を採用する場合は、十分な不正対策を取る必要があります。まず、全従業員に対して労働時間の考え方や自己申告の方法、事業者側が申告の不正をしないことを説明しなければなりません。
事業者は自己申告が適切に行われているか確認するために、定期的な実態調査が求められます。従業員の実労働時間と自己申告の時間の間で大きな乖離が生じていないか調査することが大切です。また、従業員の不正防止のために、自己申告の時間だけでなく、タイムカードなどの客観的な記録との乖離が生じていないか確認もしておきましょう。
逆に従業員が過小に申告しているケースもあるので、実労働時間よりも自己申告の時間の方が少ない場合も注意することがポイントです。
賃金台帳は使用者が項目ごとに事項を記入する
賃金台帳は使用者が、労働日数や労働時間数などの事項を記入する必要があります。主な賃金台帳の項目は以下のとおりです。
- 労働日数
- 労働時間数
- 休日労働時間数
- 時間外労働時間数
- 深夜労働時間数
労働日数や労働時間数に加えて、休日労働時間数や時間外労働時間数、深夜労働時間数の記録は大切です。これらの時間は割増賃金になるため、分けて記録しなければ適正な給与を計算できません。
適正な給与の算出ができなければ、従業員とのトラブルに発展する可能性が高いです。休日出勤や時間外労働、深夜労働は、従業員にとって大きな負担になるので、対価を払うために細かく記録しましょう。
出勤簿やタイムカードなど労働時間に関する書類は5年間保管する
出勤簿やタイムカードなど労働時間に関する書類は、5年間保管しなければなりません。
労働基準法第109条において、始業・終業時刻など労働時間の記録に関する書類の保管が義務付けられています。保管が義務付けられている書類は以下のとおりです。
- 使用者が自ら始業・終業時刻を記録したもの
- タイムカードなどの記録
- 残業命令書及びその報告書
- 労働者が自ら労働時間を記録した報告書
以前は3年間の保存義務でしたが、現在は保存期間が5年に延長しているので注意しましょう。ちなみに、保存期間の起算点は、書類を最後に更新した日です。たとえば、2022年4月1日に書類を更新した場合、5年後の2027年3月31日まで保存する必要があります。紙で記録している方は、5年間保存するためのスペースを確保しておきましょう。
労働時間の管理をする者には問題の把握や解消の責任もある
労働時間の管理者は、管理上の問題を把握し解消することも仕事の1つです。つまり、人事労務担当役員や人事労務担当部長など労務管理を行う部署の責任者は、労働時間を適切に管理するための課題を早期発見し、迅速に対処することが求められます。たとえば、以下のようなことに注意しなければなりません。
- 労働時間が適正に把握されているか
- 過重な長時間労働が行われていないか
- 労働時間管理上の問題点があればどのような措置を講ずべきか
労働時間の管理だけでなく、適切に管理をするための取り組みが求められます。労働時間の管理方法に問題がないか定期的に確認しましょう。
必要に応じて労働時間等設定改善委員会などを活用する
必要に応じて労働時間等設定改善委員会を活用することが大切です。労働時間等設定改善委員会とは、使用者と従業員で構成されたメンバーで、労働時間に関する事項を話し合う組織です。
労働時間等設定改善委員会を設けることで、従業員側が使用者に対して労働時間に関する意見を述べられます。従業員が使用者に労働管理の不備を伝えることで、現場と接触が少ない使用者でも、迅速に問題解消に繋げられます。労働環境は現場で働く従業員が一番熟知しているので、従業員の意見を聞く場を設けることも重要です。
出退勤時間や労働時間の適切な管理には勤怠管理システムの導入がおすすめ
出退勤時間や労働時間の適切な管理は、事業者の重要な役割です。勤務時間をより正確に管理するには、勤怠管理システムの導入をおすすめします。
スマレジ・タイムカードは、勤怠管理やシフト管理、給与計算など便利な機能が豊富です。また、アカウント作成から60日間は、すべての機能を無料でご利用いただけます。