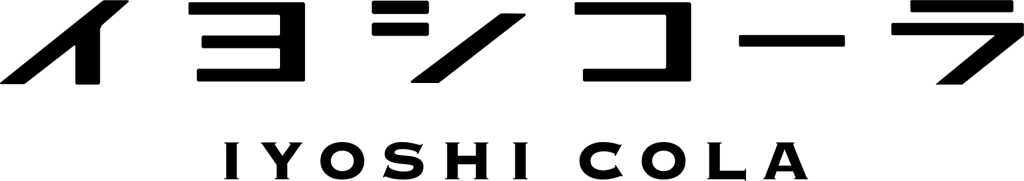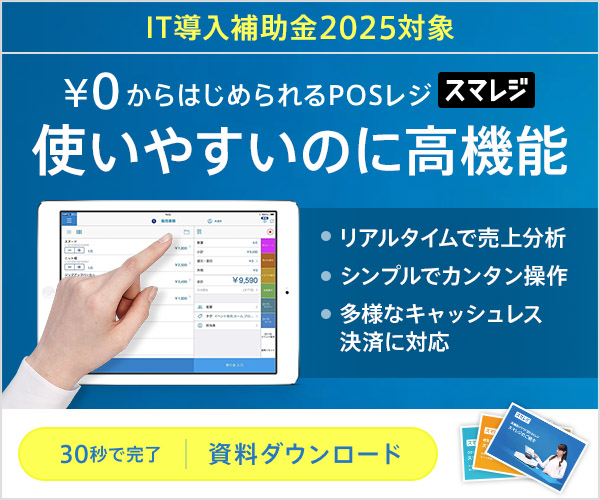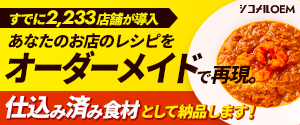about![]()
「お店ラジオ」は、店舗経営にまつわるトークラジオ番組です。小売店や飲食店など各業界で活躍するゲストをお招きし、インタビュー形式でお届けしています。この記事は、InterFM・FM大阪で毎週日曜日にお送りしている「お店ラジオ」で放送された内容を再編集したものです。
今回のゲストは、漢方職人であった祖父の技術を受け継ぎ、クラフトコーラ専門メーカー「伊良コーラ株式会社」を創業した代表取締役/コーラ職人の小林隆英さんです。独自の製法で作られる「伊良コーラ」は、伝統と革新を融合させ、和牛や高級バーなど、こだわりの場面で愛されている一品です。
祖父から受け継いだ漢方技術をもとにクラフトコーラ「伊良コーラ株式会社」を創業し、伝統と革新を融合させたユニークなコーラを作り出すまでの経緯、そしてその商品がどのようにして特定のシーンで強く共感されるようになった背景や、今後の展開について、3回に分けてお送りします。
第1回は、クラフトコーラとの出会い、クラフトコーラのコンセプト、「伊良コーラ」の誕生などについてお送りします。
この記事の目次
コーラ職人が作る「伊良コーラ」
伊良コーラ(IYOSHIコーラ)は、東京・下落合に工房を構えるクラフトコーラ専門メーカーです。
私は漢方職人であった祖父の技術と工房を受け継ぎ、この会社を創業しました。現在、伊良コーラ株式会社の代表取締役社長を務めると同時に、自ら「コーラ職人」としてクラフトコーラの製造に携わっています。この「コーラ職人」という肩書きは、非常に珍しいものだと思います。
私の祖父は漢方職人で、私の実家で漢方薬局向けに生薬を加工して納める仕事をしていました。これが、私がコーラを作ることになった一つのルーツです。しかし、私にはもう一つのルーツがあります。
それは「コーラマニア」として、世界中のコーラを飲み歩いていた経験です。南米やヨーロッパなどでは、地元のソーダメーカーが独自のコーラを作っていて、スーパーには3種類や4種類ものコーラが並んでいることがよくありました。私はそういった様々なコーラを飲んで楽しんでいました。
私は、大学を卒業後、広告会社で働いていましたが、アメリカの都市伝説的な記事で、「コカ・コーラのレシピが漏れた」という話を見つけました。
そこにはシナモンやクローブ、カルダモンといった、私がよく知っているスパイスの名前が並んでいて、「コーラは自分で作れるのか」と驚きました。これが、私がコーラ作りを始めるきっかけでした。
クラフトコーラは大手のコーラとは違う飲み物
私は当初、全く知識がなかったため、スパイスとレモンやライムを煮込んでシロップを作り、それを炭酸水で割って飲んでみました。結果は意外にも不味くはなく、「コーラ風味」のシロップができ、可能性を感じました。
「これを世に出したら、何かすごいことが起きるのではないか」と思い、そこから試作を重ねていきました。
ご存知ない方も多いかもしれませんが、コーラのルーツは実は漢方にあります。コーラには、漢方やチャイに通じる要素が含まれており、東洋人にとってどこか馴染みのある味と感じるかもしれません。
私は、日本の食文化や水、そして偶然にも持っていた漢方の知識を活かし、コカ・コーラとは異なるアプローチでコーラを作ることができると考えました。つまり、コカ・コーラとは違うフィールドで勝負できると感じたのです。
これまで、コカ・コーラやペプシが市場をほぼ独占している中で、多くの挑戦者が敗れてきた背景には、コカ・コーラが作った「ルール」に従って戦おうとしていたことがあります。
私は、クラフトコーラは全く別の「競技」であり、名前は「コーラ」ではありますが、全く異なる飲み物だと考えています。

ニッチなマーケットで強く共感してもらえるクラフトコーラ
コカ・コーラはファストフードと一緒に飲まれることが多いですが、伊良コーラは和牛や高級バーなど、全く違うシーンにマッチしています。また、銭湯や釣りといったシチュエーションで、お風呂上がりや釣りの後など、しみじみと楽しんでもらえる場面でも人気があります。
最近では、吉祥寺のこだわりのミニシアター「アップリンク」でよく飲まれており、非常に売れています。大手のシネコンなどではコカ・コーラが合うかもしれませんが、「アップリンク」のようなこだわりのある映画館では、伊良コーラがよりフィットしていると思います。
そのため、吉祥寺や中目黒など、こだわりを持ったおしゃれな人々に支持されており、そういったシーンが少しずつ広がっています。
このように、私たちは大手企業とマス市場で直接競争するのではなく、ニッチな市場や特定のシーンで勝負しています。そこでは、コカ・コーラのような大手がカバーしきれない顧客層やシチュエーションに、私たち独自の魅力を提供できるのです。
特に、クラフトコーラのように地元の素材や文化を反映した商品は、そうしたニッチなマーケットで強く共感を得られると感じています。

祖父の工房で見つけたヒント
クラフトコーラの研究を始めてから、すぐに美味しいコーラができたわけではありません。実際、2年半もの間、成果が出ずに低空飛行が続き、「もうやめようか」と思ったほどです。
なかなか納得のいく味にならず、スパイス一つとっても、ホールのまま使うか、すりつぶすか、また柑橘類についても、レモンの皮だけを使うか、全体を使うか、さらには皮を乾燥させるかどうかなど、無限に試行錯誤の余地がありました。
あらゆる変数をノートに記録しながら試していましたが、どれも決定打にはならず、「もう限界だ」と感じていました。
そんな時、漢方職人であった祖父が他界し、遺品整理をすることになりました。私が実家のある下落合に戻り、祖父の漢方工房を整理していた時、「こんな作り方をしていた」と家族が話しているのを聞き、私はその作り方に驚きました。
そして、それがコーラ作りに応用できるかもしれないと考え、早速家に帰って試してみたのです。すると、それまでとは全く違うものが出来上がったのです。
「伊良コーラ」の誕生
煮方や焼き方、つまり火の入れ方など、それまで私が行っていた火の入れ方とは全く異なっていました。詳細はお伝えできませんが、私はそれまでは常識的に「煮込む」という方法を取っていましたが、祖父の火の入れ方を試してみたところ、驚くほど違う香りを持つシロップが出来上がりました。
そして、そのシロップを友人に飲んでもらったところ、真顔で「これ、いくらなら売ってくれるの?」と言われました。その瞬間、「これなら売れるかもしれない」と思い立ち、すぐに知り合いの車屋さんに電話してキッチンカーを作ってもらい、3ヶ月後には「伊良コーラ」として青山のファーマーズマーケットでの販売を開始しました。
当初は、キッチンカーでプラスチックのパウチにシロップを入れ、炭酸水とレモンスライスを加え、ストローを差して500円で販売していました。しかし、いきなり「伊良コーラです」と言っても、ほとんどの人が「何だこれは?」と思ったはずです。
最初の出店では、150杯分を用意して本当に売れるのかとドキドキしていましたが、青山ファーマーズマーケットに出店したところ、大行列ができて一瞬で完売しました。
まだ、世の中になかったクラフトコーラという概念
完売した理由の一つは、「クラフトコーラ専門店」という看板を掲げたことが大きかったと思います。当時、世の中にはまだ「クラフトコーラ」という概念がなかったため、多くの人が「なんじゃこりゃ?」という反応をしていました。
おそらく、みんなクラフトコーラを一度は飲んでみたいと思ったのだろうと感じています。これが一つ目の理由です。
もう一つの理由として、大行列の予兆が実は販売開始の3日前にすでに現れていました。キッチンカーを作った後、友人と一緒に「セッティングがちゃんとできるか不安だ」と思い、多摩川の河川敷でキッチンカーの組み立て練習をしていました。すると、突然自転車が一台止まり、「一杯ください」と言われました。
しかし、その時はまだ販売を開始していなかったため、「まだ売っていません。準備中です」と答えると、その人は去って行ったのですが、その時「意外と興味を持ってもらえるんだ」と感じました。
第1回は、クラフトコーラとの出会い、クラフトコーラのコンセプト、「伊良コーラ」の誕生などについてお送りしました。
第2回は、新しくおしゃれなクラフトコーラと創業の経緯、キッチンカー・シロップ・オンラインストアーの展開などについてお送りします。