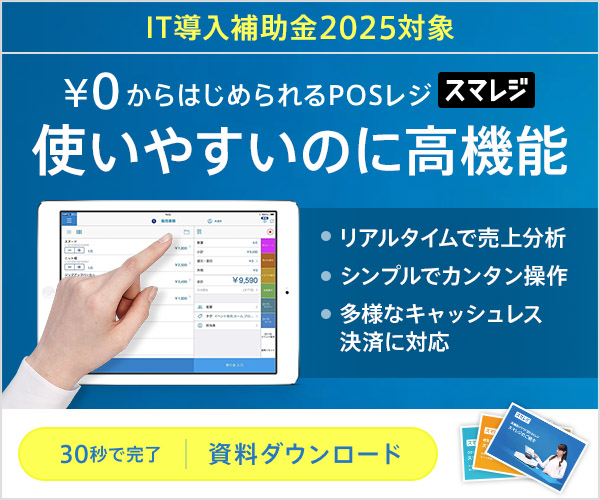about![]()
「お店ラジオ」は、店舗経営にまつわるトークラジオ番組です。小売店や飲食店など各業界で活躍するゲストをお招きし、インタビュー形式でお届けしています。この記事は、InterFMで毎週日曜日にお送りしている「お店ラジオ」で放送された内容を再編集したものです。
今回のゲストは、タビオ株式会社 代表取締役社長の越智勝寛さんです。靴下の企画・製造・販売を手がけるタビオは、「靴下屋」や「Tabio」などのブランドを国内外に展開しています。2代目として事業を引き継いだ越智さんは、靴下の履き心地とデザイン性を追求しながら、業界の発展やグローバル展開に挑戦し続けています。
靴下専門店『タビオ』が誕生し、業界における独自の地位を築くまでの挑戦、品質と履き心地を追求するものづくりの哲学、そして国内外での展開や靴下文化の普及を目指す取り組み、さらに、スポーツソックスやEコマースなど新たな分野での挑戦を通じて、靴下業界全体の成長を目指す未来への展望などについて、3回に分けてお届けします。
第1回では、株式会社タビオの創業秘話、靴下専門店「靴下屋」の誕生や、業態を確立するまでの挑戦についてお送りします。
この記事の目次
靴下専門店の挑戦~タビオの創業~
株式会社タビオは、大阪市浪速区に本社を置き、靴下の企画・製造・販売を行う企業です。1968年に創業し、1977年に株式会社ダンを設立しました。現在は「靴下屋」や「tabio」などのブランドで、直営店やフランチャイズ展開を行っています。
私は2代目で、父が創業者です。父は愛媛県出身で、中学卒業後、大阪の靴下小売店で修行を積み、1968年に「ダン」を創業しました。「ダン」という名は、「男一匹でやる」という思いから付けられました。
当初は卸売業が中心でしたが、1983年に久留米商店街で靴下専門店「靴下屋」1号店をオープンしました。そのきっかけは、神戸三宮の地下街で1坪のスペースを靴下で埋めてほしいという依頼があり、ポップアップのような店舗を作り、成功したことでした。この成功を見た久留米のオーナーが本格的な店舗展開を提案し、現在の業態の基盤となりました。
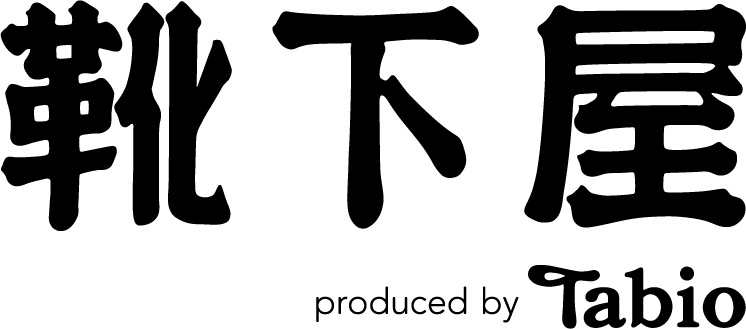
靴下専門店の挑戦~季節変動を克服~
靴下は「買い物のついでに購入するもの」というイメージを持たれる方が多いと思います。そのため、靴下単体で専門店として運営するという業態は、商売としてイメージしづらい部分があるかもしれません。
年間売上を月別で見ると、6月・7月・8月の夏場は全体の約2%程度にとどまります。一方で、12月・1月の冬場には単月で20%を占めるほど売上が集中します。このような季節変動のため、夏場に資金が不足して秋冬物の仕入れが難しくなるという、資金繰りにおける悪循環が生じる可能性があります。
他の業態では、夏場に水着や下着など季節に応じた異なる商品を販売することで、この時期の売上を補うケースもあります。しかし、私たちのように靴下のみを扱う専門店では、それが難しいため、例えば店舗のオープン時期を秋に設定するなど、細かな工夫を重ねてきました。
これにより、最初の資金が確保された状態で事業をスタートさせ、季節変動による課題を乗り越えることができています。
靴下を代わりに販売してくれる専門店
当初、靴下はショップの一角に靴下が少し置かれている程度の目立たないアイテムでしたが、靴下自体はそれなりの価格帯の商品であったため、専門店としてしっかり展開することで可能性はあると感じていましたので、市場の状況を調査し把握することに努めました。
そして、専門店として豊富な商品を揃え、見やすく陳列し、ポップを活用して分かりやすく説明するなど工夫をし、さらに、スタッフに対しては商品の特性を丁寧に説明できるよう徹底的に教育を行いました。そうした取り組みが、大きな差別化のポイントとなり、久留米で始めたお店は成功することができました。
その成功の後、九州各地のオーナーたちが興味を持っていただけるようになり、次々と新しい店舗をフランチャイズ形式で展開していくことになりました。こうして九州を中心に店舗網が広がり、さらに北上する形で全国へと展開していきました。
しかし、最初からフランチャイズ(FC)形式で展開したとはいえ、当時は、FCビジネスと明確に意識していたわけではなく、「靴下を代わりに販売してくれる専門店を運営してくれるオーナーさん」というイメージに近いものでした。まるで棚貸しのような軽い感覚でスタートし、「最終的に何百店舗作ろう」という明確なビジョンがあったわけではありませんでした。
履かれない靴下は『クズの下』
靴下の購買単価については、驚かされることが多々あります。ある店舗では、一人のお客様が一度に5,000円から6,000円分を購入されることもあり、「こんなに靴下が売れるのか」と驚かされることも少なくありません。
印象深いエピソードとして、中国の店舗での出来事があります。あるオーナーが「このモールは人通りが少ない」と話しており、午前中に来店したのはわずか2人でした。それでも売上はすでに45万円に達していたのです。この話を聞いたときは本当に驚きました。国内では銀座シックス店が特に高い売上を記録していて、インバウンドのお客様や高付加価値商品を求める方が多く、まとめ買いによって売上が何億円規模に達することもあります。
靴下は消耗品であり、年に2回程度のリピート購入が一般的です。特に男性の場合、履き心地が悪い靴下は使われずタンスの中で眠ることが多いため、私たちは「先発ローテーションに入る靴下」を作ることを重視しています。会長も「履かれない靴下は『クズの下』だ」と語り、履き心地と品質を追求し続けています。
かかとがずれにくさが快適さを左右する
靴下は、買い物のついでに購入し、1〜2回履いた後に片隅に置かれ、1年後には捨てられることが多いものです。私自身もそのような経験があります。しかし、そうならない靴下を作るため、私たちは特に「かかと」の部分にこだわっています。
一般的には効率を重視してかかとを小さく編むメーカーもありますが、私たちは昔ながらの方法でしっかりとした大きさのかかとを作ります。これにより靴下がずれにくくなり、お客様が快適に履き続けられるようになります。少しでもかかとがずれると、その靴下は二度と履かれなくなることが多いため、手間を惜しまず「ずれない靴下」を追求しています。
具体的には、靴下には「表糸」と「裏糸」があり、裏糸は伸縮性がある一方で表糸にはありません。そのため、編み方で伸縮性を調整し、「20〜22センチ対応」と記載された靴下でも実際には幅広いサイズに対応できるよう工夫しています。足の形状に応じて適切に伸びてフィットする靴下を作るのが私たちの強みです。
特にかかとの部分を編む際は機械のスピードが落ち、生産効率が下がります。しかし、効率よりも履き心地を優先することで、かかとのずれにくい、丁寧に作られた靴下を提供しています。このようなこだわりが、靴下の快適さを大きく左右すると考えています。
履き心地とデザイン性の両立
靴下作りにおいては、つま先の処理も非常に重要です。つま先がゴワつくと履き心地が悪くなりますし、甲の部分に生地が余ると、厚手の靴下を履いて革靴を履いた際に上側が余り、快適さが損なわれることがあります。こうした細かいポイントにも細心の注意を払っています。
また、ゴム口のフィット感も重要な要素です。これは個人の好みによる部分が大きく、ゆるめを好む方もいれば、しっかりとした締め付け感を求める方もいます。さらに、つま先を強化した靴下を好む方もいれば、つま先で破れた経験がないため補強を不要とする方もいます。
これらの多様なニーズに応えるため、私たちはさまざまな品番を揃えています。女性の靴下ではファッション性が重視されることが多いですが、履き心地の良さを追求する点は共通しています。
私たちは履き心地とデザイン性を両立させるために長年研究を重ね、細部にこだわった靴下作りを通じて、多くのお客様に満足いただける商品を提供できるよう努めています。
靴下が消耗品からファッションアイテムとして認識
靴下の品質や履き心地を追求する中で、事業が自然に拡大した部分もあれば、ヒット商品が成長のきっかけになった部分もあります。
1990年代にはルーズソックスが大流行し、「大きければ良い」という時代のニーズに応える商品が求められました。その一方で、私たちからトレンドを提案し、新しい市場を作ることもありました。
2000年代には、カラータイツやストレッチレースのソックスといった新しい商品をリリースし、アパレル業界に変化をもたらしました。これらのヒット商品をきっかけに、駅ビルや郊外のショッピングモールからの出店依頼が増え、事業が拡大していきました。
特に1990年代中盤以降、靴下が消耗品からファッションアイテムとして認識されるようになり、若い世代の支持を得て来店者が増加。それに伴い、会社の方向性をファッションに寄せるようになりました。

第1回では、株式会社タビオの創業秘話、靴下専門店「靴下屋」の誕生や、業態を確立するまでの挑戦についてお送りしました。
第2回では、靴下の履き心地を追求した商品開発や季節変動への対応、中国市場での成功事例についてお送りします。