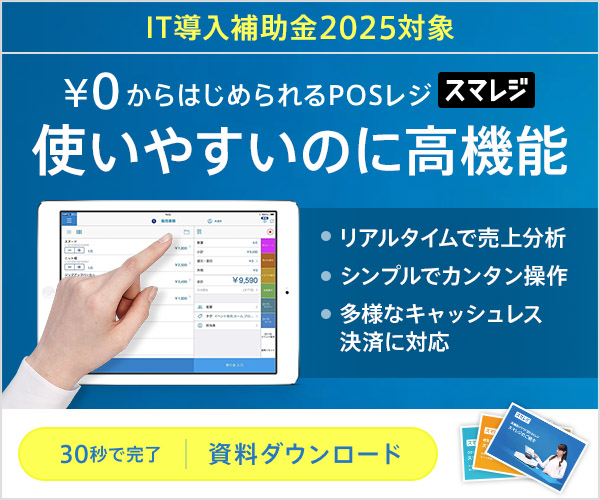about![]()
「お店ラジオ」は、店舗経営にまつわるトークラジオ番組です。小売店や飲食店など各業界で活躍するゲストをお招きし、インタビュー形式でお届けしています。この記事は、InterFMで毎週日曜日にお送りしている「お店ラジオ」で放送された内容を再編集したものです。
今回のゲストは、sio株式会社の代表取締役です。「美味しさ」を超えた感動体験を提供することで幸せを届けることを目指し、料理人としての経験を活かした独自の料理哲学と革新的な経営スタイルで、多様な店舗運営やレシピ開発、PR活動に取り組んでいます。
「おいしいを超えた感動体験を提供する」という理念のもと、レストランの運営から戦略立案、商品開発まで幅広く活動し、ミシュラン星を獲得。星を失った後もさらに挑戦的な姿勢で、顧客体験を重視した新しい飲食ビジネスへの挑戦の背景や戦略を3回に分けてお送りします。
第1回は、星を失った後の再挑戦、顧客に感動を届ける理念、「美味しい」をデザインすることなどついてお送りしました。
第2回は、「価値を表現する場」としてのレストラン運営やスタイル重視の運営などについてお送りします。
この記事の目次
青山らしさとsioの個性の融合
現在、12月にリブランドする「sio青山」のコンセプトワークは自分で手がけています。青山は洗練された大人の街というイメージが強いため、それを丁寧に分解・分析し、「sio」の個性を融合させています。
例えば、青山の顧客層は、洗練された大人の雰囲気やシンプルな美しさを好む傾向があり、また多皿のコースが好まれます。しかし、「sio」らしさを出すために、少し複雑な料理も組み込み、さらにエレガントな雰囲気に合う料理や内装を検討しながら全体の方向性を決定しています。
青山には働く人と住む人の両方が訪れますが、特に住んでいる方の利用が多いと考え、ターゲットを微調整しています。また、代々木上原店と同じ価格帯にすることで、「sio」に親しみを感じているお客様が青山店も気軽に訪れやすくなり、シーンに応じて両店舗を気軽に使い分けられるよう工夫しています。
「価値を表現する場」としてのレストラン運営
青山の店舗をハイエンド路線にしようという意見や、家賃の高さを考慮した収益最適化の提案もありましたが、私たちは単に収益を追求する場としてだけでなく、レストランを「価値を表現するショーケース」として捉えています。そのため、収支がトントンでも構わないと考えています。
私たちの実際の収益源はコンサルティングやプロデュース業であり、レストランはそれを支える役割です。私たちは3〜4年前から、『レストランは価値を表現するショーケースである』という考え方のもと、プロデュース業に注力するようになりました。レストランが「ショーケース」として価値を持てるかを重視しています。
例えば、居酒屋は初期投資が少なく2〜3年で回収可能ですが、レストランは回収に7年ほどかかり、運営のみでの利益は難しいです。そのため、レストランは単なる利益追求ではなく、意義や価値を込めた「グランドデザイン」に基づいて運営しています。
一つ星がもたらしたショールームとしての価値
ミシュランで一つ星を獲得できたことで、私たちのレストランはショールームとしての価値は確実に高まりました。狙ったわけではありませんが、「星を取りたい」という意欲から、最初から料理やサービスを徹底的に研究し、独自のスタイルを工夫しました。
その当時、パリで「ビストロノミー」が注目されており、私たちも「イノベイティブなビストロ」として評価されることを目指しました。パリでみたテーブルクロスのないカジュアルなレストランを見たとき、「このスタイルは日本にも通用する」と直感し、ワインリストやテーブルクロスを排除した新しいスタイルを導入しました。
このアプローチは、単なるフランス料理やイタリア料理ではなく、イノベイティブな存在として注目され、感度の高いクリエイター層からも支持を受けました。結果的に、この独自性が高評価につながり、一つ星を獲得できたのだと思います。
スタイルよりもスタンスを重視するレストラン運営
私が重視しているのは、表面的な「スタイル」ではなく、信念としての「スタンス」です。広く百人に好かれるよりも、深く共感してくれる十人を大切にし、「かっこいいことしかやらない」という姿勢で、写真映えを意識することよりも、空間そのものの雰囲気や食事の本質にこだわり、あえて暗めの照明を取り入れています。
私たちのターゲットは、この価値観に「かっこいい」と共感してくれる人たちであり、流行に左右されず、逆張りの姿勢で唯一無二の価値を届けたいと考えています。
ミシュランの星を失ったことは、自分たちの実力や価値観を試す良い機会です。私たちには自信もロジックもチーム力も備わっていて、他と異なる道を選ぶ勇気もあります。私たちは、他店が主流のスタイルに倣う中で、あえて逆張りの挑戦を続けることで、その先に新しい価値が見えると信じています。未知の領域にあえて踏み込む覚悟で、次のステージに向かっています。

世界を目指す戦略と多様な業態への挑戦
「sio」がミシュラン一つ星を取得し、世界展開を考えた際、複数店舗が必要だと感じました。そして、丸の内に出店、その後渋谷にパーラーを展開するなど、急速に拡大を進めました。ギリギリの綱渡り状態でしたが、世界を目指すにはこの挑戦が不可欠だと考えていました。
「sio」を複数展開するのが一番わかりやすい方法だったのですが、私には天邪鬼なところがあり、すき焼きや居酒屋など異なる業態で経験値を積みたいと思ったのです。そのため、丸の内では「ナチュラルワイン」を中心としたイタリアン業態にし、地域にオンリーワンのポジションを築く戦略を取りました。
出店時には「ここに出すならこれだ」という閃きが重要だと思っています。例えば、丸の内は長く続く店舗が少ないエリアであり、当初ビストロスタイルを試しましたが、最終的にナチュラルワインを中心としたイタリアン業態に変更しました。丸の内にはナチュラルワインのイメージがなかったため、ここでオンリーワンの存在になれると確信しました。
当初は売上が低迷してコロナ禍で月商が300万ほどに落ち込みましたが、「ナチュラルワインに合うもの」を探求し続けた結果、シンプルで情報量が少ない料理が求められていると気づき、アンチョビを添えたゆで卵など、シンプルで手軽につまめる料理を導入することで、現在は月商1800万まで成長しています。

丸の内のブルーオーシャンに挑む
丸の内のサラリーマンはランチには来店しますが、夜は他のエリアの店へ行く傾向があります。そこで、夜でも「ふらっと寄れる」ような店構えが必要だと考えました。
また、ナチュラルワイン専門店は敷居が高いイメージがありますが、一般の方が「少しおしゃれなナチュラルワインを楽しみたい」と感じたときに入りやすい店は少ないのが現状です。そこで、27坪の小さなスペースでナチュラルワイン店を開き、ブルーオーシャンを見据えた戦略的な逆張りに挑戦しました。周囲のニーズに応え、「ウィンナー・テイクス・オール」の発想で地域に浸透させています。
1万円以上の高価格帯はシェフの腕に依存しがちですが、8000円程度の価格帯に抑えることで、社員による安定運営が可能となります。このスタイルで路面展開を視野に入れ、現在はピザもメニューに加えたイタリアンとして展開を目指しています。
ピザを加えることでテイクアウトも可能になり、店内飲食に加えて持ち帰りの売上も期待できます。これにより売上と利益率の向上が図れ、バランスの良い事業展開が可能になると考えています。
居酒屋からイタリアン、そして進化するすき焼きコース
居酒屋の展開が成功している理由の一つは、料理長に依存せず安定して運営できる再現性の高さにあります。客単価は低くなりますが安定した経営が可能になるため、再現性の高いイタリアン業態は、今後さらに展開可能であると考えています。
また、私は和食にも興味があり、現在はすき焼きのコースに力を入れています。コース形式のすき焼きメニューは長い歴史がありますが、大きな変化は見られません。そこで、このすき焼きをアップデートすることで、新たな魅力を引き出せると感じました。
通常、お客様が食べるお肉は3枚ほどなのですが、私たちはその3枚でどのように味の変化を表現するか、さらに野菜をいかに美味しく見せるかにこだわりました。また、すき焼きに至る前菜や八寸にも工夫を凝らし、フランス料理の技法を取り入れてアマダイのうろこ焼きや絶品の茶碗蒸しなどを提供することで、コース全体で感動を感じられるよう設計しています。
世界に広がる可能性を秘めたすき焼き
すき焼きは、日本の伝統的な料理として幅広い世代に愛されており、インバウンド需要や海外で受け入れてもらうことも期待できる一品です。また、すき焼き弁当としても展開が可能ですし、誰もが一度は食べたことがあるため、こだわりや違いが伝わりやすいという強みもあります。
例えば、私たちのすき焼きメニューでは佐賀の黒木農園から仕入れた糖度13%のレンコンを使用し、割り下で煮込んで卵とともに召し上がっていただきます。糖度13%のレンコンを煮込むことで、シャキシャキとした食感と甘みを引き出し、ご飯との相性を際立たせています。
さらに、すき焼きに最適な米の炊き方にもこだわっていて、粒立ちが良く、硬めで芯のない食感に仕上げています。食材選びにも妥協はなく、特にすき焼きに合うお米については、実際に産地を訪問し、すき焼きに最適な米を追求しています。
このようなこだわりにより、私たちのすき焼きは国内外で今以上に愛される可能性を秘めており、世界へ発信できる料理としての価値を高めていると思います。
第2回は、「価値を表現する場」としてのレストラン運営やスタイル重視の運営などについてお送りしました。
第3回は、青山での挑戦と人材育成、これでよいと思われていたものを改善する姿勢などについてお送りします。