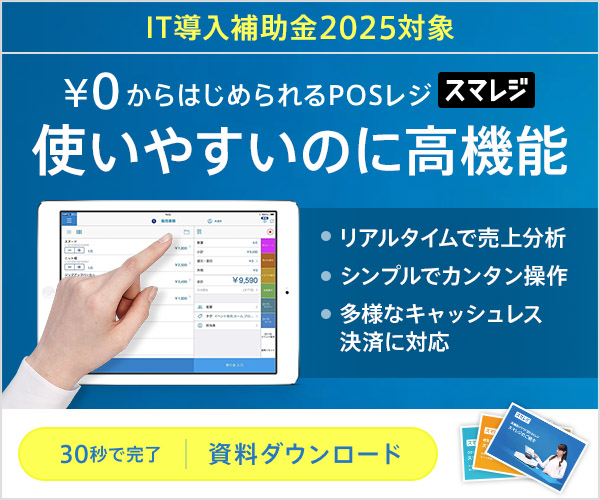about![]()
「お店ラジオ」は、店舗経営にまつわるトークラジオ番組です。小売店や飲食店など各業界で活躍するゲストをお招きし、インタビュー形式でお届けしています。この記事は、InterFMで毎週日曜日にお送りしている「お店ラジオ」で放送された内容を再編集したものです。
今回のゲストは、sio株式会社の代表取締役です。「美味しさ」を超えた感動体験を提供することで幸せを届けることを目指し、料理人としての経験を活かした独自の料理哲学と革新的な経営スタイルで、多様な店舗運営やレシピ開発、PR活動に取り組んでいます。
「おいしいを超えた感動体験を提供する」という理念のもと、レストランの運営から戦略立案、商品開発まで幅広く活動し、ミシュラン星を獲得。星を失った後もさらに挑戦的な姿勢で、顧客体験を重視した新しい飲食ビジネスへの挑戦の背景や戦略を3回に分けてお送りします。
第1回は、星を失った後の再挑戦、顧客に感動を届ける理念、「美味しい」をデザインすることなどついてお送りします。
この記事の目次
星を逃して挑戦的になった
sio株式会社は、「おいしいを超えた感動体験を届けることで世の中を幸せにする」ことを目指し、レストランの運営から店舗・レシピ開発、戦略立案、PRまで幅広く行っています。
私たちが経営する「sio」は、もともとオープンして1年余りでミシュランの一つ星を獲得していましたが、2023年にミシュランの一つ星を失いました。しかし、それを機に「好きなことに集中しよう」と改めて決意することができました。
星があった頃は評価を気にして守りに入っていました。しかし、今で、私服で働き、好きなアートや音楽を取り入れる開放的なスタイルに変えたことで、予約が取りづらい人気店へと進化しました。
私は社員に対して、「お客様のためにどこまで努力できるか」が重要で、特に予約の電話対応を丁寧にするよう常に指導しています。予約が取れない場合であっても、他の時間を提案したり、別の店舗を紹介したりするなど、お客様にとって最善の方法を探る姿勢を大切にしています。
コンシェルジュのように柔軟に対応し、「ぜひうちに行きたい」と言ってくださるお客様に対し、最善を尽くすための努力を惜しみません。電話はお客様との大切なタッチポイントであり、接客の一部として大切にしています。

サッカー少年から料理人へ
私は、高校卒業後、すぐに料理人を目指したわけではありません。「サッカー少年」として大人になり、JFLの練習生としてサッカーを続ける一方で、小学校の先生もしていました。しかし、現場での教育に疑問を感じ「ボランティアならともかく、報酬をもらってやるのは違う」と思い、別の道を探すことにしました。
そして、やりたいことや、やりたくないことをリスト化しました。定時勤務が嫌で、私服で通勤したい、音楽やファッションを楽しめる仕事がしたいなどと考えるうち、カフェで働くことを思い立ちました。
しかし、カフェで働くようになったものの、たまに訪れるプロの料理人に「素人だ」と見られているようで肩身が狭く感じ始めました。私は、「このままではいけない」と考えるようになりプロの料理人のもとで修行することにし、料理人の道を本格的に歩み始めることになりました。
料理への情熱と独立への決意
私が修行を始めたのは31歳の頃でした。その当時はお金や経営のことなど考えず、ただ「料理がうまくなりたい」という思いだけでした。しかし、働くうちに「この店で働く」から「表現をしたい」という気持ちが強くなり、同時に独立への意識が芽生えるようになりました。
当時、私は任された料理に自分なりのアレンジを加えながら、料理を「自分ごと」として考えられるようになっていましたので、約7年の修行を経て独立の準備が整ったと感じました。そして、辞めて独立することも考えましたが、私が店を離れることで次のシェフが苦労することを懸念し、その店を買い取る決断をしました。
資金調達も容易ではなく父親に家を担保にしてもらい1000万円を借り、さらに以前のカフェのオーナーが内装の手配を手伝ってくれたことで、何とかオープンにこぎつけることができました。オープン準備で特に大変だったのは、5月末に買い取った店舗を一度閉め、わずか一ヶ月半後の7月20日に再オープンするタイトなスケジュールでした。
クリエイター層に響くこだわりでミシュランの星
私は常に料理のロジックを意識してレシピを作っていましたので、アイディアに困ることはありませんでしたので、「どんなお店にするか」をしっかりと考えました。6000円であった以前のメニュー価格を、思い切って1万円に設定し、「クリエイターに評価される店」を目指すことにしました。私は、フーディー層ではなく、起業家やクリエイター、広告業界の人々に響くような店作りを目指したのです。
さらに、店のロゴデザインは「くまモン」を手がけた水野学さんに依頼しヒップホップが流れ、テーブルクロスのないスタイルにしました。ストリートカルチャーを愛する私は、ファッションブランドの関係者や起業家に「センスがある」と感じてもらえるような空間づくりを徹底しました。結果、オープンから約1年後にミシュランの星を獲得することができたのです。

お店を「プレゼンの場」に、情熱を伝える接客
私は、お店は「プレゼンの場」であると考えていて、お客様に自分の思いやこだわりを伝えることを大切にしています。例えば、一日15人の来店客の中で2人に私の思いが届けば、月に約50人に届きます。そして、その中の1人くらいは本気で応援してくれる人がいるかもしれない、という気持ちで熱意を伝え、「いつか世界に進出する」という夢を語り続けました。
お客様とのトークはお店のこだわりから始まり、料理や備品一つひとつに込めた思いを説明します。例えば、最初のスープは次の料理を引き立てるため薄味にしていて、すべてが計算された味の組み立てであることなどです。こうした私の思いをお客様に伝え、ロジックに基づいた料理の魅力をお客様と共有するのです。
また、「味のKPI」という言葉で、レシピの代わりに味の評価基準で管理している点を話すと、特にビジネスに馴染みのあるお客様からは興味を持たれます。このような会話が噂となり、共感する人々が徐々に集まるようになっていきました。私の仕事はアーティストではなく、「クライアントワーク」だと思っています。お客様に満足していただくことを最優先し料理を提供するだけでなく、お客様とのつながりを大切にしています。
私の仕事は世の中の需要を見極める「クライアントワーク」
私は、お気に入りのブランドがあると、企業からの依頼がなくても勝手にアレンジレシピを作りツイッターで拡散するなど、好きなブランドのPRを行っていました。
また、新しい料理は、最初にツイッターやコース料理などで反応を試し、最初のリアクションを見てさらに革新的なものを投じます。3回ほど試作を重ねた後、確信が持てれば、一気にアクセルを踏んで展開します。このようにして、需要を見極め、「これだ」と感じたら一気に行動に移すのが私のやり方です。
コロナ禍には、レシピを無料で公開しました。当時、レシピで収益を上げる時代が来るかもしれないと思いつつも、「レシピの収益化は自分がやるべきことではない」と判断し、すべてを無料でオープンソース化しました。
手軽で身近なレシピで「美味しい」を作れる世の中にしたい
私は、レシピ作りにおいては「再現性」「材料の手に入りやすさ」「家庭での作りやすさ」が重要だと考えています。特にコロナ禍ではこれらの要素にこだわり、1ヶ月ほど家にこもってレシピ開発に専念しました。
例えば、家庭で手に入りやすい材料を活用したり、セブンイレブンの商品を使ったアレンジレシピを開発するなど、手軽で親しみやすいアイデアを心がけています。こうした「すぐに試せる」スピード感のあるアレンジは、SNSでバズりやすいのです。
私はこうした「バズる」要素をストックし、編集して新しい形で発信しています。ゼロから作り上げるのではなく既存のものに工夫を加え、あたかも新しいもののように見せることで、多くの人に喜んでもらえるのが私の喜びです。
他の料理人が自分のレシピを真似することは全く気にしていませんし、むしろ、自分の「美味しい」の考え方を、ギットハブのようにみんなでシェアしたいと思っています。誰もが「美味しい」を作れる世の中になることが、私の目指す理想です。

「美味しい」をデザインする
「美味しいホールディングス」を設立したのは、「美味しさ」をデザインするという理念の一環です。私には「美味しさ」を生み出すロジックがあり、それは「味覚的な美味しさ」と「外的要因」を掛け合わせたものです。「美味しさは」味覚だけでなく体験の総合力で決まると考えています。
例えば、富士山頂で食べるおにぎりと、こたつで食べるおにぎりでは、環境によって味の印象が異なるように、『美味しさをデザインする』という視点で仕事をしています。
飲食店を始める人には、まず「目的」と「手段」を明確にすることを勧めています。単に「1000万円を稼ぐ」が目的ではビジョンが広がりません。「何のために店をやるのか」を考え、目的に最適な業態を選ぶことが重要です。
そのため、私のコンサルでは、「何が良くないか」を診断することを重視しています。多くの人は処方箋を出しますが、診断ができる人は少ないと感じています。クライアントの目的に対して上流から考え、具体的なレシピ提案も含めて包括的にアドバイスを提供します。
さらに、大企業では1%のロス削減で年間2000万円の利益が得られることもあります。この材料を使って新メニューを作れば利益が倍増する場合もあり、こうした数値改善にも力を入れています。KPIが決まれば選択肢が明確になり、スムーズに進行できます。
第1回は、星を失った後の再挑戦、顧客に感動を届ける理念、「美味しい」をデザインすることなどついてお送りしました。
第2回は、「価値を表現する場」としてのレストラン運営やスタイル重視の運営などについてお送りします。