
企業の労務担当者のなかで、勤怠控除の正しい考え方や計算方法を知りたいと考えている方もいるでしょう。
この記事では、勤怠控除の意味や、勤怠控除ができないケース、勤怠控除の適切な方法や勤怠控除を適用するときの注意点について解説します。
この記事の目次
欠勤控除(勤怠控除)の意味。「ノーワークノーペイの原則」に基づいた考え方
勤怠控除とは欠勤控除の通称で、もともとの支払う予定の賃金から欠勤した分の賃金を差し引くことをいいます。
欠勤控除の根幹には「ノーワークノーペイの原則」があり、働いていない分は報酬を支払う必要がないという考えで成り立っているルールです。
ノーワークノーペイの原則は直接的に規定が定められているわけではありませんが、一般的な考え方として定着しています。
欠勤控除は欠勤日だけでなく、遅刻や早退など、労働時間が短い日も対象です。つまり、3時間遅刻して出勤した場合は、3時間分の賃金が差し引かれて給料が支払われるということになります。
労働基準法における「減給の制裁」とは?
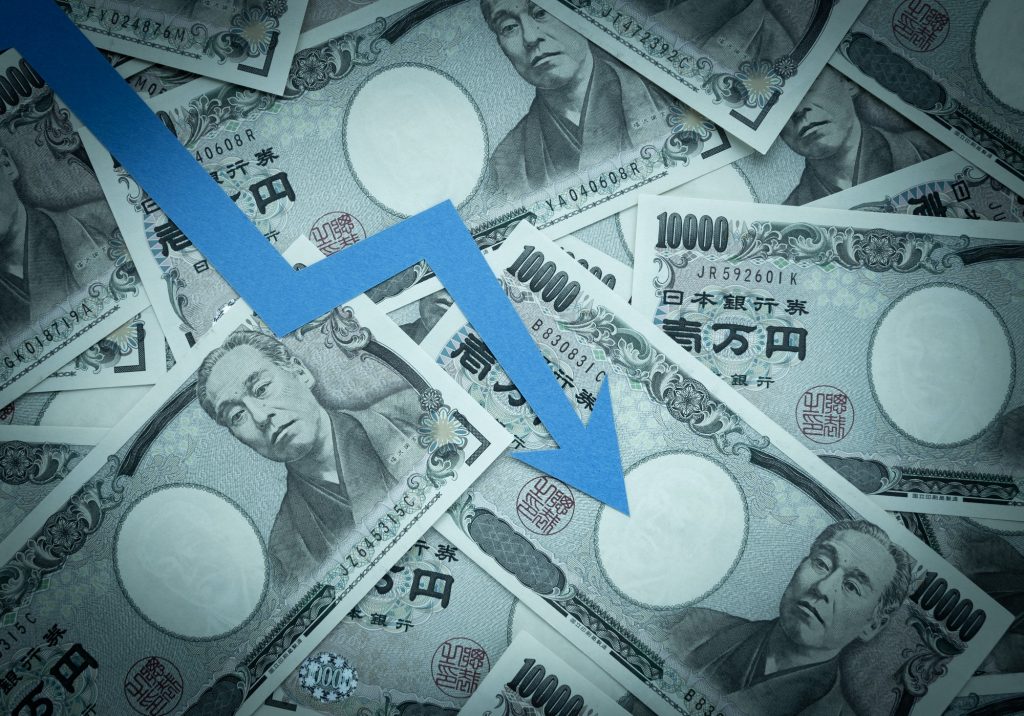
欠勤控除とは別に労働基準法には「減給の制裁」という制度があります。
減給の制裁とは、従業員が契約違反をしたときにペナルティとして減給することが許される制度のことです。
ただし、事業者の裁量で自由に減給できるわけではなく、2つの制限が設けられています。
- 1回当たりの減給額は、平均賃金1日分の半額を超えてはならない
- 賃金支払期間において、減給額は賃金総額の10分の1を超えてはならない
たとえば、1日の平均賃金が1万円だった場合、実労働時間が予定労働時間の半分に満たなくても5千円までしか減額できないということです。
また、1カ月の基本給が20万円の場合、最大でも2万円までしか減額してはならないということになります。減給できる上限が決められているため、労働基準法を遵守した範囲で欠勤控除を行いましょう。
欠勤控除を適用できない場合
全てのケースで欠勤控除が適用できるわけではありません。
従業員の個人的な理由により欠勤、もしくは遅刻・早退した場合は欠勤控除が適用できますが、有給休暇や会社都合の休業の場合は適用できません。
2つのケースにおいて、なぜ欠勤控除ができないのか解説します。
有給休暇
有給休暇を使って休んだ場合は、欠勤控除が適用できません。もともと出勤する予定だった日を対象に有給休暇の申請を行い、申請が通って休んだ場合は、急な休みでも欠勤扱いにはならないのです。
就業規則には有給休暇を使用した日に対して、定められた金額を支払う義務が生じます。形式上は欠勤でも就業規則に定められた正規の手続きを行って休んでいるため、有給休暇使用日を減給の対象にすることはできません。
会社都合の休業
会社都合で休業した場合は、当然ながら欠勤控除や減給の制裁の対象にはなりません。従業員には全く過失がないにもかかわらず、会社の指示により休んでいるため、欠勤控除を適用することができないのです。
なお、会社都合の休業によって従業員を休ませる場合、休業手当として平均賃金の60%以上を支払わなければなりません。
法律で欠勤控除の規定はない
欠勤控除は法律上に規定がありません。そのため、欠勤控除を理由に賃金を減額する場合は、従業員とのトラブルを防止するために、就業規則にしっかり明記しておく必要があります。
どのような違反を行ったときに、どのくらいの限度で給料が減額されるのか、誰が読んでも理解できるように明記することが重要です。
たとえば、遅刻や早退をした場合、平均労働時間から時給を換算した後に、予定労働時間よりも少ない分だけ減額するといった内容を記さなければなりません。
また、就業規則に記すだけでは従業員が欠勤控除の仕組みを理解していない場合もあるため、従業員を採用する際に、欠勤控除に該当するケースや欠勤控除の計算方法などをしっかりと説明しておきましょう。
勤怠控除の給与計算方法

勤怠控除の給与計算する方法は以下の4パターンです。
- ① 月の給与÷年平均の月所定労働日数×欠勤日数
この計算式を用いた場合、以下のような計算をすることになります。
『勤怠控除額=(基本給+諸手当)÷年平均の月所定労働日数×欠勤日数』
ちなみに、年平均の月所定休日日数は『(365日-年間の所定休日日数)÷12ヶ月』で算出できます。
この計算式は、該当する月の所定労働日数が21日で20日間欠勤した場合は、月の給与と勤怠控除額が同額になります。
勤怠控除がこの1カ月のみだった場合は違法とはなりませんが、1日勤務していても給料がゼロになるので、この場合は他の計算方法を活用した方がよいでしょう。
- ② 月の給与÷該当月の所定労働日数×欠勤日数
この計算式を用いた場合、以下のような計算をすることになります。
『欠勤控除額=(基本給+諸手当)÷該当月の所定労働日数×欠勤日数』
1月と2月のように月の所定労働日数が異なるため、この計算方法を用いる場合は、該当月の所定労働日数を算出した後に行いましょう。
- ③ 年間の給与÷年の暦日数×欠勤日数
この計算式を用いた場合、以下のような計算をすることになります。
『欠勤控除額=(年間基本給+年間諸手当)÷年の暦日数×欠勤日数』
年の暦日数は、365日のときもあれば366日のときもあります。
- ④ 月の給与÷該当月の暦日数×欠勤日数
この計算式を用いた場合、以下のような計算をすることになります。
『欠勤控除額=(基本給+諸手当)÷月間の暦日数×欠勤日数』
③の月で計算するパターンです。月によって28日、29日、30日、31日の4パターンあるので、該当月の暦日数を確認しておきましょう。
なお、上記4パターンの計算方法を活用する際は、基本給だけでなく通勤手当や資格手当など労働に直接影響がある諸手当も加えて計算しなければなりません。
各種手当が欠勤控除の対象となるかどうか以下の表にまとめたので、手当を設けている事業者は計算時の参考にしてください。
- 手当
- 手当内容
- 勤怠控除の対象
- 通勤手当
- 通勤費用を補助する手当
- 〇
- 扶養手当
- 扶養家族を持つ者に支給する手当
- ×
- 住宅手当
- 住宅にかかる費用を補助する手当
- ×
- 資格手当
- 業務に有効な資格を所有している者に支給する手当
- 〇
- 役員報酬
- 管理職に対する報酬
- ×(長期にわたる欠勤の場合は、取締役会で減額を決定できる)
勤怠控除を適用する際の注意点・トラブルを防ぐポイント
勤怠控除を適用する際に注意すべきポイントがあります。特に、就業規則への明記と労働基準法の遵守は意識すべきポイントです。
従業員とのトラブルの元となるので、これから解説する2つの注意点を頭に入れて、適切に勤怠控除を行いましょう。
就業規則に明記する
勤怠控除に関する内容は全て就業規則に明記するようにしましょう。
たとえば、欠勤や遅刻・早退によって控除される適応要件、勤怠控除の計算式など控除の詳細を就業規則に記すのが重要です。
特に、欠勤や遅刻・早退においてどのようなケースで勤怠控除が適用されるのか記す必要があります。
また、勤怠控除が適用される場合、どのような計算によって賃金が減額されるのか、明らかにしておくのがポイントです。
勤怠控除の計算方法に関しては、先述したように各種手当を含めた場合にどのような計算になるのか記しましょう。
特に通勤手当や営業手当など労働に直接影響するものは、勤怠控除の対象になる旨も明記しておくことでトラブル防止につながります。
労働基準法を違反しないように注意する
勤怠控除を適用するにしても、労働基準法に違反しないことが大前提です。
実際に減額対象となるのは、欠勤や遅刻・早退によって予定労働時間より実際に少なくなった時間のみで、ペナルティーとして減額対象となる時間以上に控除をすると違反になります。
会社の風紀を整えるために「見せしめ」として罰則を与えるという考え方もあるかもしれませんが、賃金の減額は裁量の範囲内に留めておきましょう。
なお、労働基準法における勤怠控除に関する注意すべきポイントは以下の2つです。
- 実労働時間に対する賃金が最低賃金を下回ると違法になる
- 会社都合の休業や有給休暇の場合は欠勤控除が適用できない
ノーワークノーペイの原則が一人歩きしてしまうと労働基準法に違反してしまうため、少なくともこれら2つのポイントは意識しておきましょう。
トラブルのない勤怠管理のためにはクラウドシステムが有効
勤怠控除を適用するときは、労働基準法に違反しないように注意する必要があります。法律で規定がなく適用できないケースもあるため、就業規則に明記して適切に処理しましょう。
なお、勤怠控除などのイレギュラーにも適切に対応するためには日頃から正しく勤怠管理を行っていることが大切です。スマレジ ・タイムカードを利用すれば、勤怠管理を徹底しトラブル防止を抑制することができます。












