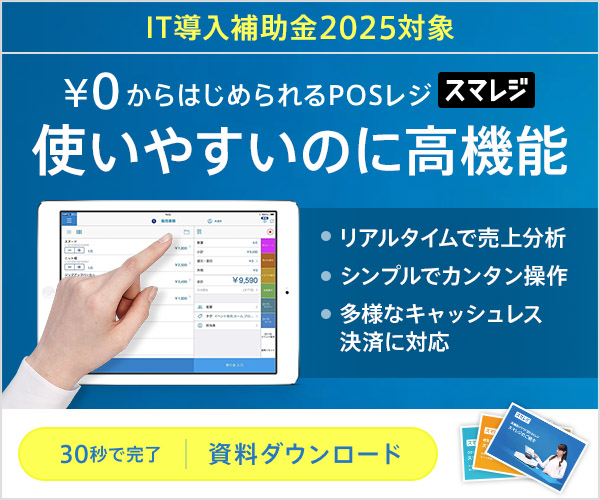about![]()
今回のゲストは、飲食業や店舗プロデュースなど幅広い事業を展開されている、株式会社ガネーシャ代表取締役本田大輝さんです。実家の焼肉店「大将軍」を再生させた後、ハンバーガーブランド「SHOGUN BURGER」を立ち上げ、地域や海外に合わせた独自の戦略で成功を収めています。
実家の焼肉店「大将軍」の再生からスタートし、接客の質やマーケティング戦略を駆使して繁盛店へと成長させ、ハンバーガー事業「SHOGUN BURGER」を立ち上げ、和牛を使った高級バーガーを展開。挫折と改善を繰り返しながら東京や沖縄で成功を収め、今後は海外展開も視野に入れたビジネス戦略について、3回に分けてお送りします。
第1回は、実家の焼肉店「大将軍」の再生と繁盛店へ導くサービスの三大要素などについてお送りしました。
第2回は、新たな業態への挑戦、「SHOGUN BURGER」の誕生と挫折と成功などについてお送りします。
この記事の目次
新たな業態への挑戦と撤退「サムギョプサル店」
実家の焼肉店の経営が安定した後、私は新たな業態や店舗展開に挑戦しました。以前サムギョプサルのお店で働いた経験を活かし、最初に立ち上げたブランドが「豚魔神」でした。ニューヨークのカフェのようにスタイリッシュな店内で、サムギョプサルを楽しむ空間を作り上げました。
「豚魔神」は富山で大人気となり、その後名古屋にフランチャイズ展開し、東京にも進出しました。この成功の理由は、おしゃれな雰囲気と、当時珍しかったサムギョプサルを組み合わせた新しいスタイルの新鮮さにあったと思います。
しかし、韓国料理のブームが到来して競合が増え、同時にコンビニでも韓国関連の商品が次々と登場しました。チャミスルを1700円で提供していた時代から、今ではコンビニで、200円ほどで買えるようになり、価値を維持するのが難しくなりました。当時、3500円だったマッコリが、現在では400~500円で販売されるなど、価格競争が厳しくなってきました。今では、一時的なブームからすっかり定着した感があります。
また、豚肉や野菜の仕入れ価格が上昇し、原価率も20%台から40%台に達し、焼肉店と同等のコストとなりました。加えて、若い世代の酒離れが進み、お酒より「映え系」商品の人気が高まったため、次第にこの業態への興味を失ってしまいました。結果、「豚魔神」を続けるのは難しいと判断し、次の展開を考えるようになりました。
焼肉フランチャイズの難しさと新たな挑戦「SHOGUN BURGER」
焼肉店のフランチャイズ展開を試みた経験から、私は焼肉のような複雑なオペレーションはフランチャイズには不向きだと感じました。オーナーが覚えるべきことが多く、難易度も高い上に、人気の先輩店との競争が厳しく、成功を掴むのは非常に困難でした。資金が尽きそうになることも度々あり、経営の難しさを痛感しました。
そんな中で、何か一発逆転のアイデアはないかと考えていた時に、私がスタッフ向けに作っていたハンバーガーが頭に浮かびました。「和牛のハンバーガー屋をやったら面白いかもしれない」と思い立ち、次のステップへと繋げることにし、「大将軍のハンバーガー」というコンセプトのもと、「SHOGUN BURGER」を立ち上げました。ハンバーガーに兜をかぶせたデザインと、日本風のロゴを採用し、まずは地元富山でテスト店舗をオープンしました。将来的には、インバウンド客が集まる歌舞伎町に出店し、ここをショールームとして海外のお客様にもアピールすることを目指していました。
富山での成功を確信した後、満を持して歌舞伎町に二号店をオープンしましたが、予想以上に改装費用がかさみ、最終的には5000万円近くかかり、会社の資金はほぼ底をつきました。それでも、兜のロゴや和牛の味には自信があったため、一世一代の勝負として挑みましたが、オープン当初は売上が全く伸びず、1日の売上が6〜7万円程度という厳しい現実に直面しました。

挫折からの再起と「スマッシュ」技法の導入
当初、友人やフーディーのシェフたちは応援してくれていましたが、「美味しくない」「東京のレベルに達していない」と辛辣な指摘を受けました。この言葉にはショックを受けましたが、何とかお店を維持するために、昼のランチから深夜5時まで働き続け、バーのような形で営業を続けていました。主に夜のアルコールの売上で経営を支え、友人たちが飲みに来て応援してくれたのです。
そんな中、参考にしたのが「ヘンリーズバーガー」でした。焼肉の名人、中原さんが手掛けたこのハンバーガー店で、特に注目したのが「スマッシュ」という調理技法です。この技法は、和牛のミンチを丸めて熱した鉄板で押しつぶしながら焼く、アメリカでは一般的な調理法ですが、日本ではまだ珍しいものでした。
この技法を取り入れ、何度も試行錯誤を重ねました。徐々に美味しいハンバーガーが作れるようになり、フーディーたちからも「美味しい」と評価されるようになりました。これをきっかけに売上も伸び、味の追求とともに認知度も上がり、店の状況も好転していきました。
商品改良と口コミ戦略での成長
味や肉の品質をさらに追求し、スマッシュ技法を維持しつつも、バンズや肉のレシピに手を加えていきました。しかし、小さな企業であるがゆえにバンズを製造してくれる業者が見つからず、最終的には自分たちで毎朝までかけてバンズを作ることになりました。
その結果、20坪ほどの小さな店舗でも月商が1000万円を超え、最終的には1500万円にまで成長しました。この売上の伸びは、商品改良だけでなく、私が得意とするマーケティング戦略が大きく寄与していたと思います。特に、インバウンド向けの施策に力を入れ、トリップアドバイザーや中国の口コミサイト「大衆天評」での露出を強化し、ホテルへの営業も積極的に行いました。
特に、トリップアドバイザーなどの口コミサイトでの評価を上げることが、観光客を呼び込む重要な要素となりました。口コミやネット上の情報がなければ、歌舞伎町を訪れる外国人観光客も店に足を運んでくれません。私自身も旅行の際に口コミを参考にするため、ネット上の情報の重要性を強く感じ、この戦略が集客に大きく貢献したのです。

行列を生むための努力と粘り強さ
店舗の売り上げが1500万円に達すると、店の前には行列ができるようになりました。行列ができると、それを見た人たちが「美味しそうだ」と思い、ラーメン屋のように自然と並んでくれるようになりました。
しかし、その行列を作るためには、地道な営業やマーケティングの積み重ねが不可欠でした。特に、インバウンド向けのレビューや口コミ評価を少しずつ積み上げることが重要です。最初は反応がなくても、ある瞬間、突然「ドーン」とお客様が増えることがあります。
ただし、多くの人はその瞬間まで粘り強く待てず、途中で諦めてしまうことが多いのです。「何をやってもダメだ」という声もありますが、実際には十分にやり切れていないケースが多いと感じています。成功には継続することが鍵だと考えています。
私自身も、家賃が120万円という厳しい歌舞伎町で、資金面や精神面で追い詰められていました。毎日大きなストレスを抱え、飲み倒れてしまいそうになることもありましたが、地道な努力を続けた結果、少しずつ成果が現れ始めたのです。
コロナ禍でのチャンスと積極的な拡大
コロナ禍の緊急事態宣言中、私たちが偶然にもウーバーイーツを導入していたことが大きな成功の鍵となりました。ウーバーイーツでの注文が急増し、少人数(ツーオペやワンオペ)でも月に1000万円の売上を達成することができたのです。
その後、メディアにも多く取り上げられ、海外からの観光客がいなくてもビジネスを維持できる状態にまで成長しました。こうした状況の中で、フランチャイズに興味を持つ方が現れ、最初のフランチャイズ店舗として秋葉原店がオープンしました。
さらに、コロナの影響でテナントが減少していることに気づき、渋谷のセンター街で好条件の物件を見つけ、将軍バーガー渋谷店を出店しました。この店舗は大成功を収め、コロナ禍でも守りに入ることなく、積極的に出店を進めることができました。
第2回は、新たな業態への挑戦、「SHOGUN BURGER」の誕生と挫折と成功などについてお送りしました。
第3回は、出店戦略とインバウンド、高級バーガーのファストフード、竜宮城への支援などについてお送りします。