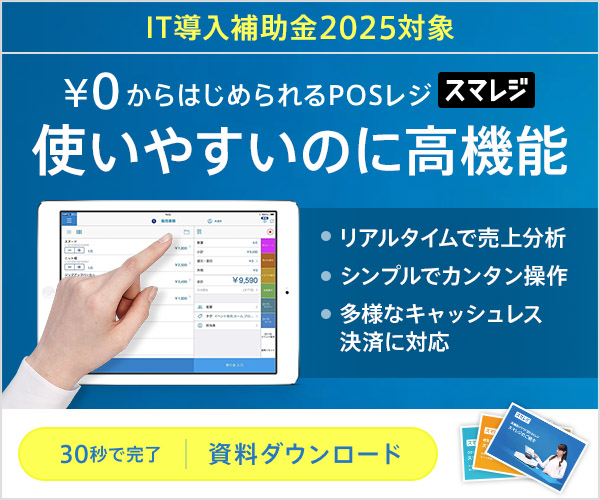about![]()
「お店ラジオ」は、店舗経営にまつわるトークラジオ番組です。小売店や飲食店など各業界で活躍するゲストをお招きし、インタビュー形式でお届けしています。この記事は、InterFMで毎週日曜日にお送りしている「お店ラジオ」で放送された内容を再編集したものです。
今回のゲストは、タビオ株式会社 代表取締役社長の越智勝寛さんです。靴下の企画・製造・販売を手がけるタビオは、「靴下屋」や「Tabio」などのブランドを国内外に展開しています。2代目として事業を引き継いだ越智さんは、靴下の履き心地とデザイン性を追求しながら、業界の発展やグローバル展開に挑戦し続けています。
靴下専門店『タビオ』が誕生し、業界における独自の地位を築くまでの挑戦、品質と履き心地を追求するものづくりの哲学、そして国内外での展開や靴下文化の普及を目指す取り組み、さらに、スポーツソックスやEコマースなど新たな分野での挑戦を通じて、靴下業界全体の成長を目指す未来への展望などについて、3回に分けてお届けします。
第1回では、株式会社タビオの創業秘話、靴下専門店「靴下屋」の誕生や、業態を確立するまでの挑戦についてお送りしました。
第2回では、靴下の履き心地を追求した商品開発や季節変動への対応、中国市場での成功事例についてお送りしました。
第3回では、靴下をファッションアイテムとして広める取り組みや、グローバル市場での挑戦と地域特性を活かした展開についてお送りします。
この記事の目次
中国市場で広がる靴下文化
成長戦略において、Eコマースや海外展開は重要なテーマです。その中で、中国での展開が好調であり、私たちの靴下を高く評価してくれるオーナーとの出会いが成功の鍵となっています。
現在、中国では約33店舗を展開し、一流ブランドが並ぶエリアに出店しています。高級ブランドの隣に店舗を構えることで、商品が高付加価値の商品として認識され、軌道に乗りました。また、百貨店や一流モールにも進出しています。
私たちは、中国で「Made in China」を誇りに思っていただきたいという願いを込めて、私たちがプロデュースし、中国の工場で生産した靴下を販売しています。さらに、中国市場に合わせた工場の開発も進め、「我が国の靴下は素晴らしい」と思っていただける靴下文化の普及を目指しています。
もちろん、「メイド・イン・ジャパン」というブランド力も中国市場で重要な要素です。しかし、「メイド・イン・ジャパン」だけに頼り切ることは単なる驕りであり、それに依存しない姿勢を持つことが大切だと考えています。
最近では、中国の工場の品質は向上しています。この進化は日本の工場にも刺激を与え、切磋琢磨の関係を作ることで、国内製造業の奮起を促すことにもつながると信じています。
業界全体が100年後も存続できる基盤を作る
日本での生産能力には物理的な制約があり、全てを日本製品に頼り、輸出を増やすだけでは限界があります。国内で100%生産しても需要を賄うことが難しいのが現状です。
私たちは、日本製品を守りつつ海外の工場とも共に成長し、靴下業界全体を活性化させるバランスを大切にしています。検査基準や品質管理のノウハウを日本と中国で共有化し、両国の工場が共に高品質の製品を生産する仕組みを作ることで、業界全体の成長を目指しています。
私たちは量を増やすだけの生産拡大には興味がありません。目的は、業界全体が100年、200年後も存続できる基盤を作ることです。売上の追求ではなく、安定した利益を出し続けること、そして健全な経営を通じて工場との協力関係を築くことが、私たちのビジネスの本質だと考えています。
時代によってはウェブが主流となることもあれば、リアル店舗が再び注目されることもあります。その時々の変化に柔軟に対応しながら、「時代に合った事業を展開している」と認識される企業でありたいと考えています。上場企業であっても、無理に売上を伸ばし続けることを目標とせず、靴下業界全体の健全な存続と長期的な持続可能性を追求することが、私たちの使命です。
目指すのは靴下業界の番頭
私たちは、商品ラインナップを靴下以外に広げることは考えていません。各業界には専門性の高い企業が多く、無理に他分野へ進出することはリスクが大きいと判断しています。
多品目を扱う企業を否定するわけではありませんが、私たちは「靴下業界の厄介な門番」のような存在を目指しています。「日本製の靴下を守る」という使命感を持ち、業界の衰退を防ぐための努力を続けています。そのため、靴下業界でニッチトップのポジションを維持することが目標です。
社内からは「他分野へ進出すべき」という意見もあります。しかし、私たちは靴下業界にはまだ強固なポジションを築く余地があると感じています。これまで培ってきた付加価値をさらに磨き上げ、この分野で圧倒的な存在感を持つ企業を目指します。
地域特性を活かした海外展開と物流戦略
海外展開では、中国以外の市場にも注力しています。アメリカ市場では、インターネット販売を4年前から進めており、まだ大きな成果は出ていないものの、SNSを活用してコミュニティ形成に努め、日本とは異なるビジネスモデルで、お客様を囲い込む戦略を模索しています。
イギリスでは、20年前にロンドンに店舗を開設し、現在も1店舗が営業中です。ただし、同市場ではインターネット通販が主流となってきたため、リアル店舗を縮小し通販を強化しています。
一方、パリではリアル店舗の需要が依然として強く、現在3店舗を展開中です。リアル店舗を中心としながらも、インターネット通販を並行して行っています。さらに、韓国では1店舗、中国では33店舗を展開し、地域ごとの市場特性に応じた戦略を取っています。
物流面では、靴下が季節商品である特性を考慮し、鮮度を重視しています。輸送には飛行機を利用し、コストはかかるものの、タイムリーな商品提供を優先しています。この季節商品の特性に合った物流体制によって、お客様の満足度向上を図っています。
ネット戦略とリアル店舗
国内のイーコマースでは、「ネットだけでは購入に結びつきにくい」と考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、現代のお客様はまずネットで情報を集めるのが一般的です。ネット上に情報がない商品は、そもそも選択肢にすら入らないため、ネットでの商品情報提供は欠かせないのです。
私たちは、ネットで商品を知り興味を持ったお客様が、最寄りの店舗で実物を確認できる仕組みを整えています。SNSやホームページなどが充実していなければ、店舗で商品を手に取ってもらうことも難しい時代になっています。現代では、ネットを通じた認知や検討のフェーズを経ずに商品を購入することはほとんどないからです。
そのため、ネット通販やSNSを無視した運営では、リアル店舗の売上が上がることはないと考えており、この分野に力を入れるため、新たな人員を増やし戦略を見直し、購入プロセスを簡略化するシステム構築にも取り組んでいます。
私たちの業界では、名前が知られていない会社であっても、ネット戦略を強化すれば、数年で業績を大きく伸ばすことが可能です。これが、ネットとリアル店舗の連携の重要性を示しています。

地域文化を尊重した靴下のグローバル展開
アメリカでのEC展開は、英語圏全体への販売につながる可能性があります。しかし、靴下業界特有の事情も存在します。
基本的に、靴下を日常的に履く女性が多いのは東アジアだけであり、これは靴下専門店が文化を育んできた結果だと考えています。世界的には、靴下を履く習慣が根付いていない地域が多くあります。例えば、ヨーロッパでは女性がサンダルや生足でジーンズを履くことが一般的で、靴下は必要なときだけ履くものという認識が強いのです。「靴下を履いてファッションを楽しむ文化」が根付いているのは、ほぼ日本に限られると言っても過言ではありません。
靴下文化の異なる市場では、現場の感覚を尊重し、地域に根付く方法で運営することを心がけているため、20年以上店舗を運営しているロンドンなどは、商品展開は現地スタッフに一任しています。本部から指示を出さず、現地のスタッフが現場の感覚で品揃えを決定しています。同様に、アメリカのEC展開でも現地チームに運営を任せており、これがグローバル市場で成功するための鍵であると信じています。
地域特性とグローバル需要を活かした靴下市場の新たな可能性
靴下は夏場に売上が落ちるため、東南アジア市場は適さないと思われがちです。しかし、過去に東南アジアで年間売上2,000万円を達成し、単一の売り場としてトップの成果を出したことがあります。この実績から、暑い地域でも靴下が売れると実感しています。
創業期には、最も売れたのが沖縄で、北海道では売れないという事例がありました。これは、市場の成熟度や地域特性が大きく影響していると考えられます。北海道のような地域では靴下の販売チャネルが整っている一方、競合が少ない沖縄ではマーケットとして成長の余地が大きかったのです。このように、地域特性を見極めた展開が重要です。
さらに、スポーツ分野では国境を超えた需要が広がっています。例えば、バルセロナのクラブチームからの注文など、スポーツソックス分野でのグローバルな展開が進んでいます。競技パフォーマンスをサポートする靴下には、一定の需要が見込め、この分野の強みを活かして成長を目指しています。
私たちは、靴下業界のニッチトップとして、未開の市場やグローバルな機会を活用し、業界全体を活性化させる役割を果たしていきたいと考えています。