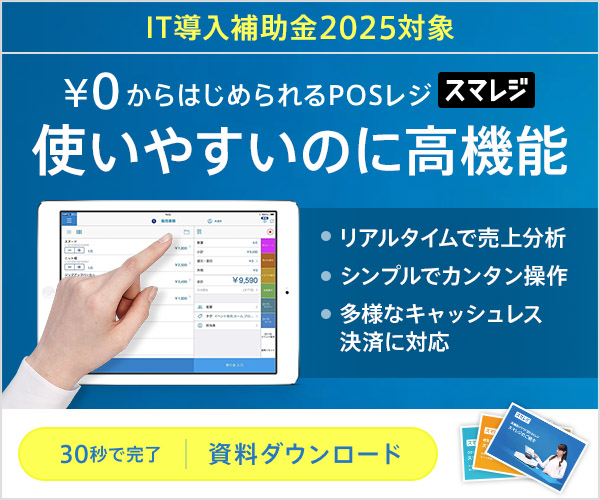about![]()
「お店ラジオ」は、店舗経営にまつわるトークラジオ番組です。小売店や飲食店など各業界で活躍するゲストをお招きし、インタビュー形式でお届けしています。この記事は、InterFMで毎週日曜日にお送りしている「お店ラジオ」で放送された内容を再編集したものです。
今回のゲストは、タビオ株式会社 代表取締役社長の越智勝寛さんです。靴下の企画・製造・販売を手がけるタビオは、「靴下屋」や「Tabio」などのブランドを国内外に展開しています。2代目として事業を引き継いだ越智さんは、靴下の履き心地とデザイン性を追求しながら、業界の発展やグローバル展開に挑戦し続けています。
靴下専門店『タビオ』が誕生し、業界における独自の地位を築くまでの挑戦、品質と履き心地を追求するものづくりの哲学、そして国内外での展開や靴下文化の普及を目指す取り組み、さらに、スポーツソックスやEコマースなど新たな分野での挑戦を通じて、靴下業界全体の成長を目指す未来への展望などについて、3回に分けてお届けします。
第1回では、株式会社タビオの創業秘話、靴下専門店「靴下屋」の誕生や、業態を確立するまでの挑戦についてお送りしました。
第2回では、靴下の履き心地を追求した商品開発や季節変動への対応、中国市場での成功事例についてお送りします。
この記事の目次
カラータイツの登場と大ヒット
当時、タイツは「防寒用アイテム」が主流で、色も黒や茶色が一般的でした。しかし、私はファッション性の可能性を感じ、カラフルなタイツを提案しました。芸大で学んだ経験から、「ブルー、ピンク、赤、パープルなど、色のバリエーションがあればファッションの幅が広がる」と考え、パッケージデザインを一新し、自ら色を選定して商品化したのです。

その結果、カラータイツは大ヒットしました。担当店舗では24色展開のタイツを打ち出し、年末には整理券が必要になるほどの行列ができるほどの人気に。店頭でカラフルなタイツが注目を集め、多くの人が「こんなタイツがあったのか!」と興味を持ってくれました。こうして、カラータイツは市場を席捲し、新たなトレンドとして広がったのです。
工場との共存共栄を大切にする取引
私たちは自社工場を持たず、奈良県や加古川など国内の優れた靴下工場と契約しています。商品づくりは、企画の依頼から始まり、使用する糸や加工方法を決定した後、工場から材料費や加工費の見積もりを受け取ります。そして、そこに一定の利益率を加えて価格を設定しています。
あらかじめ価格を決めて商品を作るのではなく、完成した商品のコストを基に価格を決めるため、原材料価格の変動によっては、価格調整が必要になることもあります。
シーズンの切り替え時に価格が上がることもありますが、適切な価格設定を常に心がけています。商品ごとに素材や加工が異なるため価格も変動しますが、例えば「1,000円を超えると高く感じられる」といった場合には、工場と再調整を行うこともあります。
私たちは「値段ありき」で安さを追求しないことを信念とし、工場の見積もりを尊重し「値引きを強要しない」姿勢を貫いています。専門店としての誇りを持ち、共存共栄を大切にしながら取引を進めています。
日本の靴下産業を永続させたい
靴下の製造には、熟練の技や感覚が欠かせません。同じ機械や糸を使っていても、工場ごとに全く異なる製品が生まれます。それぞれの工場が「より良いものを作る」という競争を続けており、この姿勢が私たちのグループの強みです。
自社で工場を持つと、生産や販売計画、在庫管理に追われる量販店的な運営になりかねません。それは私たちが目指す姿ではなく、「日本の靴下産業を永続させたい」という思いが私たちの原動力です。そのため、工場との協力体制を維持することを大切にしています。
しかし、靴下工場には事業承継の課題があります。職人の代替わりや技術継承が難しい中、翌日には新しい注文が入る現実があります。このため、「なぜこのネジを緩めるのか」「この調整がどこに影響するのか」といった細部を徹底的に研究し、技術を体系化しています。
昭和の職人技を令和の時代に継承するため、私たちは「一人の職人の技術をチームで議論しながら製品を作る」という取り組みを進めています。これこそが、本物のものづくりの現場であり、私たちが目指す姿だと信じています。チームがしっかりと体制を維持していれば、タビオから仕事がある限り、工場側も体制を維持できます。そして、靴下を工業製品として安定して生産できる仕組みを構築しているのです。
議論の積み重ねで職人を超えるチームを作る
私たちは、「良い品質とは何か」を議論し続けています。10年間、議論を積み重ねていけば、チームとして職人を超えるものを作れる可能性があると感じています。
一方で、同業他社が少ないことは課題です。競合が存在すれば、他社を参考にしながら改善点を探ることができます。しかし、それができない私たちは、売れない時期に「市場に求められていないのか」「自分たちが間違っているのか」と迷うことが多々あります。
社内では、「情熱が空回りしていないか」と振り返ることもあります。他業界であれば競合を参考にトレンドを把握しやすいですが、靴下専門店には指標がほとんど存在しないため、私たちは独自に進むべき方向を模索する必要があります。この自己判断の難しさこそが、私たちにとって大きな課題です。
季節変動を乗り越える詳細の強化
靴下ビジネスは季節変動が大きく、夏は売上が低迷し、冬に大きく伸びる特徴があります。この問題は南半球で展開しない限り完全な解決は難しいですが、現時点では南半球進出を考えていないため、季節の影響を受けにくい商材を強化しています。
特に強化しているのはスポーツソックスとメンズ向け商品です。メンズ商品は季節変動が少ないのが特徴で、ビジネスソックスやカジュアルソックスは、男性が季節や衣替えを意識せずに購入するため、安定した売上が見込めます。そうした取り組みにより、季節指数の平坦化に一定の成功を収めており、店舗単位では売上の差が残るものの、会社全体では徐々に安定してきています。
一方、女性向け商品は衣替えや冬場の防寒需要に左右されやすいため、メンズ商品の強化が季節変動の緩和に効果的です。さらに、ウェブショップでメンズ商品を展開することで、店舗に加えオンラインでも男性顧客を捉え、売上の安定に繋げています。
.jpg)
自分たちで本気のスポーツソックスを作る
スポーツアパレル市場では、大手ブランドとの競争が避けられません。特に、有名なロゴを持つメーカーの商品は、それだけで消費者に選ばれる強みがあります。スポーツ時には「そのブランドを着るのが当たり前」というイメージが根付いているため、私たちは「靴下専門店が作るスポーツソックス」という切り口で差別化を図っています。大手ブランドに企業規模で勝つことはできませんが、「本当に靴下を理解している専門家はどちらにいるのか?」という視点では勝負の余地があります。
私自身もサッカーが好きで大手ブランドの商品を愛用していましたが、靴下専門店の立場で見ると「これはただの足を覆う袋だ」と感じることがありました。その違和感から、自分たちで本気のスポーツソックスを作ることを決意しました。試作品を作り、実際に履いてプレーしてみると、水ぶくれができるなどの課題が見つかり、「もっと靴下を研究しなければ」と痛感しました。
ちょうどその頃、優秀な研究員が入社し、彼の提案でマラソンソックスの開発がスタート。その後、改良を重ねてサッカーソックスに進化させ、現在では多くのプロ選手にも愛用されています。

飛ぶように走る靴下の開発
マラソン選手を見ていると、彼らは走っているというより「飛んでいる」ように感じます。実際、選手たちは中間地点までの歩数を計算し、「この地点で何歩、このラインで踏み込む」といった感覚で走っているらしく、まさに「飛んでいる」のだと認識しました。
この発想から、私たちはジャンプに特化した靴下を開発しました。土踏まずを強化し、42.195キロの間飛び続ける動作を支える構造を採用。また、ジャンプ時の筋肉負担を軽減し、着地時のうっ血を抑える設計を取り入れたことで、選手が最後までステップを維持し、タイム向上につながる結果を得ました。
さらに、フットボールソックスの開発にも取り組み、アメフトやフラッグフットボール用の靴下を開発しました。アメリカのプロ選手にも使用してもらい、フィードバックを基に改良を重ねた結果、「文句なし」と評価される製品を市場に出すことができました。この成果により、売上が伸びただけでなく、工場の生産量も2倍に増加しました。
スポーツソックス開発の挑戦
スポーツソックスの研究開発には時間がかかり、特にこの分野では「正解」が明確でないことが多く、試行錯誤の連続です。スポーツソックスの効果は、タイムやスコアといった数値で確認することが一般的です。
例えば、マラソンでは選手のタイム改善が重要な指標となります。同時に、けがの減少や、選手自身が「パフォーマンスが体現できた」と感じるかも重要です。サッカーソックスについては、多くの選手に使用してもらいながら改良を重ねてきました。
ブランディングやマーケティングだけでは効果を判断できませんので、アスリートに実際に使用してもらいながら、満足する製品を作ることが重要です。
第2回では、靴下の履き心地を追求した商品開発や季節変動への対応、中国市場での成功事例についてお送りしました。
第3回では、靴下をファッションアイテムとして広める取り組みや、グローバル市場での挑戦と地域特性を活かした展開についてお送りします。