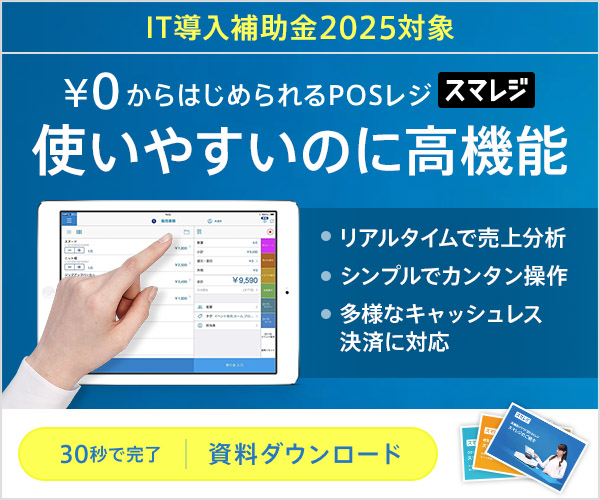about![]()
「お店ラジオ」は、店舗経営にまつわるトークラジオ番組です。小売店や飲食店など各業界で活躍するゲストをお招きし、インタビュー形式でお届けしています。この記事は、InterFMで毎週日曜日にお送りしている「お店ラジオ」で放送された内容を再編集したものです。
今回のゲストは、sio株式会社の代表取締役です。「美味しさ」を超えた感動体験を提供することで幸せを届けることを目指し、料理人としての経験を活かした独自の料理哲学と革新的な経営スタイルで、多様な店舗運営やレシピ開発、PR活動に取り組んでいます。
「おいしいを超えた感動体験を提供する」という理念のもと、レストランの運営から戦略立案、商品開発まで幅広く活動し、ミシュラン星を獲得。星を失った後もさらに挑戦的な姿勢で、顧客体験を重視した新しい飲食ビジネスへの挑戦の背景や戦略を3回に分けてお送りします。
第1回は、星を失った後の再挑戦、顧客に感動を届ける理念、「美味しい」をデザインすることなどついてお送りしました
第2回は、「価値を表現する場」としてのレストラン運営やスタイル重視の運営などについてお送りしました。
第3回は、青山での挑戦と人材育成、これでよいと思われていたものを改善する姿勢などについてお送りします。
この記事の目次
食材のウィキペディア
青山で新たにオープンする店舗では、「塩」にこだわり、全国から取り寄せた塩を料理ごとにペアリングし、それぞれの特性を活かすことで、料理の新たな楽しみ方を提案しています。
また、最近はSNS(X・旧Twitter)を活用し、より多くの人から美味しい情報を集める機会も増えました。「ヨーグルトで最高に美味しいものを探していますが、お勧めを教えてください」と投稿を通じて、多くの情報が集まり、それがまるで『食材のウィキペディア』のように他の人にも有益なリソースとなっています。
その情報は、まるで「食材のウィキペディア」のように他の人にも有益なものとなっていて、眺めるだけでも価値があると思います。また、食材情報をキュレーションすること自体がビジネスにつながる可能性も秘めており、起業を志す人にとっても注目する価値があると思います。
表参道から始まる新しい挑戦
現在、ファミリーレストランの運営にも取り組んでいます。これは、昔からの私の夢でもありました。私はロイヤルホストが大好きで、自分がファミレスを運営すれば、もっと美味しく、そして楽しい体験を提供できるのではないかと考え、この挑戦を始めました。しかし、実際には多くの課題があります。オペレーションもまだ整いきっていないため、まだ半年から1年ほどの調整が必要な状況です。
店舗は約100席規模で、ロイヤルホストのクオリティを基準にしつつ、ほんの少し価格を上げた形で運営しています。ただし、ファミリーレストランとしての親しみやすさを損なわないよう、大幅な価格変更は避けています。
長期ビジョンを見据えたチームづくりと運営のバランス
私は、日々の細かな運営は現場に任せ、私は常に5年後を見据えたビジョンの実現に注力しています。若いメンバーを中心にマネジメントを任せ、私はお客様の声に耳を傾けながら、未来への展望を描いています。
スケールしていくためには教育が不可欠ですが、同時に自分の熱意やアイディアをスタッフに共有し、チーム全体で一体感を持つことが重要です。だからこそ、スタッフを一から育てる教育の重要性を痛感しています。
私自身も早い段階から教育に取り組んできつもりではありますが、まだまだ補うべき部分もあると感じています。現場に自分がいることで直接伝えられることも多いのですが、教えすぎない教育のバランスが重要です。
店舗の規模を広げ、必要に応じて縮めるプロセスを繰り返すことで、店舗経営に芯の強さを持たせつつ、スケーラビリティを保ちながら進めていく。こうしたプロセスこそが、長期的な成功につながると考えています。これはスープ作りに例えられるかもしれません。一度濃いめに出汁を取り、必要に応じて調整を加えながら理想の味を追求するように、店舗運営やチーム作りも絶えず微調整が必要です。

料理人としての成長には、「量」と「質」のバランスが不可欠
「sio」は、選ばれた人だけが働くお店にしたいと考えており、レアルマドリードのような存在を目指しています。そのため、スタッフには非常に細かい指導を行い、私が直接料理を作らなくても高い確率で美味しい料理が提供できるようにオペレーションシステムを設計しました。しかし最近、システムが整いすぎたことで、若手スタッフが自ら考えて改善する機会を奪っていることに気づきました。
オペレーションが整いすぎていることで、若いスタッフが自ら考え改善する機会が減り、成長の場を奪ってしまっていたのです。そのため、伝え方や指示の細部にさらに注意を払い、具体的で丁寧な指導を心がけるようにしています。ディテールをしっかり伝えることの重要性を再認識し、改善を進めるのです。
また、料理人の成長には、「量」と「質」のバランスが不可欠です。ある程度の量をこなさなければ質は伴いません。特に若い世代には、まず量を積むことが大切なのです。最近は、情報が簡単に手に入る時代だからこそ、実体験が不足したまま「できた気」になってしまうことが多いように感じます。
だからこそ、実際に量を積む場を提供することが必要なのです。例えば、パスタを自主練で100回作った人と1回しか作らない人では、経験値と感覚に大きな差が生まれます。理論だけでなく、経験に基づく実践が伴ってこそ、真の成長があると信じています。
考え続け、やり続け、常に良いものを生み出し続ける姿勢
ホリエモンの「鮨屋に修行はいらない」という考え方も一つのアプローチですが、最終的には「どこを目指すか」によると思います。アカデミーで学んだ鮨職人と、20年修行を積んだ職人が握る鮨では、明らかな違いが出てくるはずで、どちらが良い悪いではなく、「何を求めてどう提供するか」によって違いが現れるはずです。
究極のシェフを目指すなら、経験と量を積み重ねることが不可欠です。80点の料理はすぐに学べますが、残りの20点を埋めるには細部へのこだわりと経験が必要です。例えば、フライパンの状況から「少し水分が足りない」と感じる微調整ができるかどうか。この直感は経験を通じてしか得られないものです。
私が大切にしているのは、「考え続けること」と「やり続けること」を両立させ、常に良いものを生み出し続ける姿勢です。

「これでいい」とされているものを改善する
最近は、「もんじゃ焼き」の業態にも取り組んでおり、私がコンサルタントとして関わることで、月商が200万円から1000万円ほどに成長しました。出汁の香りやキャベツの甘みを活かし、そば屋のような風味に仕上げたことが好評を得ています。
具材を適切なサイズにカットし全体のサイズを2/3にすることで、客単価が上がり、複数の種類を楽しみたい方にちょうど良いサイズ感を提供できるようになりました。このアプローチはピザにも応用可能で、少し小さなサイズにすることで複数の味を楽しむ機会を提供できます。
このように、既存の業態を見直しアップデートすることで、新たな可能性を切り拓くことができます。「これで良い」とされているものにも改めて目を向けることで、発見や改善の余地が見えてくるものです。
美味しさを軸にしたビジネススケールの可能性
すき焼きもそうですが、既存の料理にはまだまだ改善やアップデートのチャンスが眠っていると思います。これらの料理を「技術的な挑戦」ではなく、「世の中の人にどれだけ喜んでもらえるか」という視点から改善していくことで、結果としてビジネスのスケールにもつながると感じています。
例えば、もんじゃ焼きのような客単価が低めのメニューは、一見利益に結びつきにくいように見えますが、プロとしての視点と熱意を注ぎ、徹底的に『美味しさのレベル』を追求することで、競争力を高めることが可能です。もんじゃ焼きでは一般的に意識されていない「出汁」の美味しさに徹底的にこだわり、独自の風味を提供することで差別化を図っています。
私たちはKPI(重要業績評価指標)を「美味しさ」に設定しています。美味しさにこだわり、同時に高いレベルを追求することで、他店との差別化を図ることができます。原価を単純に上げるのではなく既存のもんじゃ焼きをさらに美味しく進化させることで再評価され、人気を集めることができるのです。このような『勝ちパターン』を確立することが、私たちの戦略において重要な鍵となります。