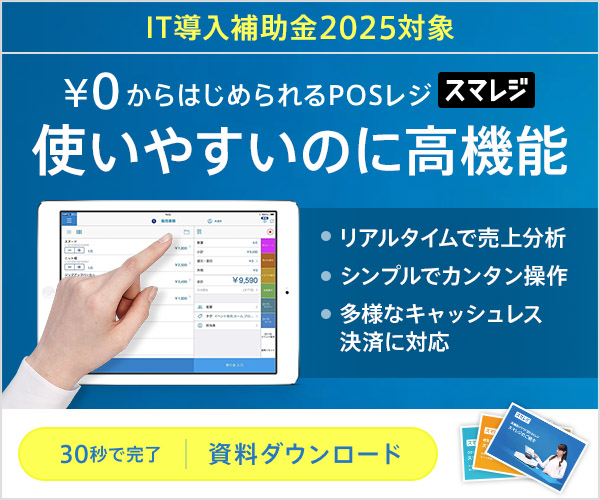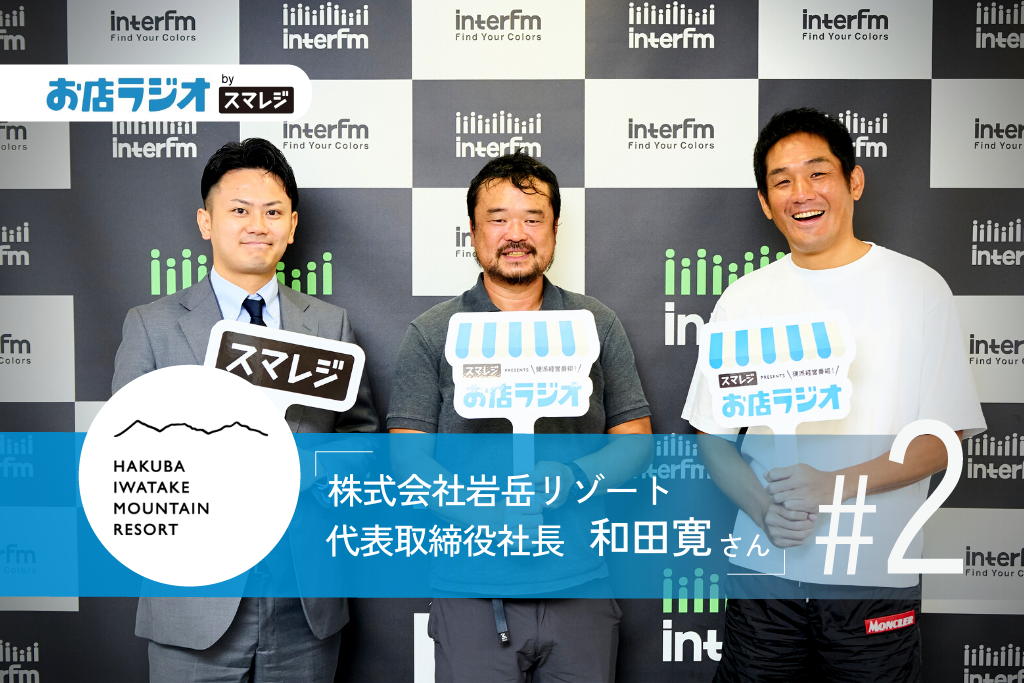about![]()
「お店ラジオ」は、店舗経営にまつわるトークラジオ番組です。小売店や飲食店など各業界で活躍するゲストをお招きし、インタビュー形式でお届けしています。この記事は、InterFMで毎週日曜日にお送りしている「お店ラジオ」で放送された内容を再編集したものです。
今回のゲストは、フランチャイズビジネスインキュベーション株式会社 代表取締役 山本昌弘さんです。同社は、フランチャイズ展開を目指す企業に特化した支援を提供し、効率的で持続可能なビジネスモデルの構築をサポートしています。また、自ら展開している、「うなぎの成瀬」の成功の鍵や、独自の業態開発における戦略や工夫について伺います。
フランチャイズビジネスインキュベーション株式会社を設立した経緯、企業の強みを活かしたフランチャイズ展開支援、そして効率的なビジネスモデルの構築や、独自業態「成瀬」や「よもぎ蒸しサロン」を通じた成功事例、さらに国内外での店舗展開戦略について、3回に分けてお送りします。
第1回は、フランチャイズビジネスインキュベーション設立の経緯や、企業の強みを活かしたオーダーメイド支援の手法などについてお送りしました。
第2回は、「成瀬」や「よもぎ蒸しサロン」の成功、人件費を抑えた効率的な運営モデルの特徴、低コストで始められる業態の魅力などについてお送りします。
この記事の目次
職人レスで切り開く新たなうなぎ市場
うなぎ業界には「串打ち3年、焼き8年、焼き一生」という言葉がありますが、私たちはこの伝統的な工程を機械化し、人件費を削減しながら、安定した品質を提供できる仕組みを構築しました。加工済みのうなぎを店舗に納品し、現場では軽く焼き直すか温めるだけというシンプルなオペレーションを実現しています。
仕込みで再度蒸す工程を加え、最後に独自の焼き入れを行う調理法を採用し、手間を抑えながらも高品質な味わいを実現しました。これにより、チェーン店などとは異なる高品質な商品を提供できるようになりました。
日本では、「安価で美味しくない商品」と「高価で手が届きにくい商品」の二極化が進み、消費者のうなぎ離れが進んでいます。そこで私たちは、手頃で購入しやすい価格帯(2000~3000円)を設定し、新たな顧客層を開拓する戦略を取りました。具体的には、2000~3000円という手頃な価格で、高品質なうなぎを提供することを目指しました。
小さな商店街から始まった挑戦
私たちの1店舗目は、プレマーケティングやリサーチをせず、横浜の平沼商店街という人通りの少ない場所に挑戦的にオープンしました。初日は約30万円の売上を記録しましたが、その後1週間で来客数が激減しました。その後の集客は試行錯誤の連続で、チラシの配布やインフルエンサーへの依頼など、様々な施策を試しましたが、どれも効果は一時的なものでした。
そんな中、あるライターが書いた「成瀬」を紹介する記事が、スマートニュースに転載されました。記事には「美味しくて格安のうなぎ屋なのに、日曜日の夜はガラガラだった。みんな行ってあげてください」と温かいコメントが添えられていました。この掲載がきっかけで、翌日には前日の売上をわずか5分で超える大反響を得ることができました。
さらに、来店したお客様がインスタグラムに投稿したり、YouTubeで動画を作成してくれたりしたことで、評判が徐々に広がりました。これらの口コミやSNSでの拡散が集客を大きく後押しし、安定した売上を築く第一歩となりました。

インフルエンサー活用で広がる集客戦略
私にとって、インフルエンサーは単なる宣伝手段ではなく、その影響力を「見込み顧客数」として捉えています。そのため、依頼する際には、影響力が高いと判断した人に絞ってアプローチしています。
この手法は、店舗数が10店舗に達するまでの主な集客手段として活用しました。新しい店舗を出店する際も、地域特性に合ったインフルエンサーを選定し、オープン時に話題を作ることで注目を集める戦略を取りました。
このアプローチは、従来のチラシ配布よりも効率的で、さらに、インフルエンサーのネットワークを活用し、地域ごとに効果的な影響を広げています。
例えば、神奈川で最も影響力のあるグルメ系TikToker「神奈川グルメ」さんに依頼したところ、その旦那さんが東京を中心に活動する「東京コスパグルメ」さんで、そこからさらに、埼玉や千葉のインフルエンサーを紹介してもらうことができました。
さらに、トップインフルエンサーの情報発信がマイクロインフルエンサーの来店を促し、さらに拡散が広がる仕組みを活用しています。
スケール可能なビジネスモデルの構築
私たちの業態は、他社に真似されるリスクを避けることはできません。しかし、多くの企業は、多店舗展開に必要なノウハウを持っていません。そのため、事業をスケールさせる能力の有無が、結果を左右します。
私たちは、焼きの工程では独自の工夫を施しています。全店舗で統一された品質を実現するため、全店舗で蒸し時間や温度設定を統一し、安定した品質を維持しています。
従来の職人技は日本文化の一部として大きな価値を持ちますが、私たちが目指すのは、より手軽に楽しめる軽飲食業態です。高価格帯の5,000~6,000円を支払う層に限定されない、新たな市場の開拓を目指しています。
機械化は、機械化により匂いなどの問題が軽減され、焼肉店などが敬遠されがちな物件でも入居ができます。通常、焼肉屋やうなぎ屋は煙や匂いの問題から物件オーナーに敬遠されがちなのですが、私たちは「軽飲食業態」であり、カフェの居抜き物件などにも入居可能なため、不動産交渉がスムーズに進められます。
このように、私たちは業態構築の初期段階から、多店舗展開を見据えた設計を行おり、オペレーションの標準化、物件選択の柔軟性、職人に依存しないモデル、これらの基盤は、スケール可能なビジネスモデルの中核を形成しています。
中価格帯うなぎ屋の新市場開拓
私たちは、中価格帯のうなぎ屋という新たな市場を開拓し、それをスケール可能なビジネスモデルとして確立することを目指しました。
1店舗目の成功を受け、2店舗目の展開に踏み出しました。2店舗目では、顧問弁護士がオーナーとなり、埼玉で物件を探し、上尾の居抜き物件を見つけ、即決しました。
一等地ではなくても成功が見込めるのは、うなぎが「食べたい」という明確な目的を持って食べられる料理であり、ラーメンなどのように「ふらっと立ち寄る」需要に依存しないためです。この特性を活かし、初期費用と家賃を抑えた分、広告費に充当する戦略を採用しました。
上尾店は、2月に大々的な広告を打たずにオープンしました。それにも関わらず、行列ができ、大きな手応えを得ることができました。そして、私自身がSNSで継続的に発信したことで、店舗への注目度が高まり、SNSの発信を通じ、フランチャイズへの問い合わせが急増しました。
千葉店での成功が証明した商店街の可能性
二号店を成功させた顧問弁護士が、「1年弱で初期投資を回収した」とSNSに投稿したことは、事業展開の可能性を感じさせました。そして、四店舗目として千葉に直営店を出店することになります。この店舗は、千葉駅裏側、千葉公園近くの閑散とした商店街にあり、以前はイタリアンレストランだった居抜き物件を活用しました。
内装は既存の状態を活かし、最小限のコストで開業しました。低コストでの立ち上げを実現したこの店舗は、22席で1日わずか6時間の短い営業時間にもかかわらず、初年度に年商1億1000万円を達成。この数字は、当初想定していた月商300万~400万円を大きく上回る成果となり、商店街の店主からも「人が戻ってきた」と感謝されるまでになりました。
この成功は、単なる店舗運営にとどまらず、地域の商店街と連携し、人々を呼び戻すことで地域活性化に寄与しました。商店街との連携や、地域の特性を活かした展開が、事業の成功と地域活性化を両立できることを証明したのです。
千葉店の成功は、立地条件の厳しい立地でも、高い収益性を実現できる可能性を示しました。限られた資金やリソースの中でどれだけの成果を上げられるかという課題に対する明確な答えとなり、次なる店舗展開への自信を深める結果となりました。
サラリーマンに支持されるスピードと気軽さ
私たちの店舗には、40代から60代のお客様が来店されます。男性が若干多く、ランチタイムには、忙しいサラリーマンの利用が目立ちます。
一般的なうなぎ屋では、提供まで30分程度かかることが多いですが、サラリーマンの昼休憩はわずか1時間しかありません。この制約の中では、ランチでうなぎを選べません。
そこで私たちは、仕込みの段階で焼きの工程を工夫し、最短5分で提供可能な仕組みを構築しました。このスピード感が、ランチ需要を取り込む大きな要因となったのです。
また、回転率を向上させるため、店舗のレイアウトにも工夫しています。私たちの店舗では4人掛けのテーブル席を減らし、カウンター席や2人掛けのテーブルを多く配置することで、1人客にも入りやすい店舗を目指しました。
こうしたスピード提供と効率的なレイアウトの工夫により、ランチタイムの回転率を大幅に向上させることができました。これまでは特別な日や土日に限られていた「うなぎ」を、平日ランチでも選べる選択肢へと変革しました。
第2回は、「成瀬」や「よもぎ蒸しサロン」の成功、人件費を抑えた効率的な運営モデルの特徴、低コストで始められる業態の魅力などについてお送りしました。
第3回は、国内外283店舗の展開戦略、物件選定やエリア計画の基準、透明性を重視したフランチャイズモデルの拡大方針についてお送りします。