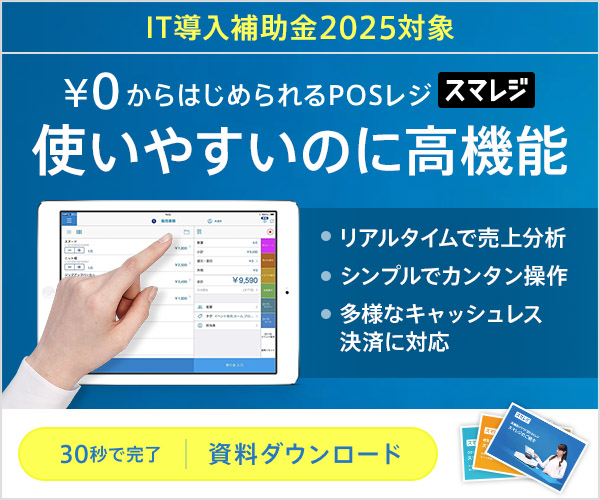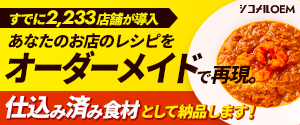about![]()
「お店ラジオ」は、店舗経営にまつわるトークラジオ番組です。小売店や飲食店など各業界で活躍するゲストをお招きし、インタビュー形式でお届けしています。この記事は、InterFMで毎週日曜日にお送りしている「お店ラジオ」で放送された内容を再編集したものです。
今回のゲストは、株式会社アイロム 代表取締役社長兼CEOの森山佳和さんです。ダイニングバー「ビーエイト」や魚料理専門の「サカナバル」を展開。また、缶詰工場の運営にも取り組むなど、飲食業界で独自の挑戦を続けています。森山さんの手がける事業の背景やこだわりについて伺います。
魚をテーマにした新業態の開発からスタートし、飲食店『サカナバル』を展開するに至った背景、恵比寿や六本木といった多様なエリアで成功を収めた戦略、さらに仕入れや経営の改善を通じて競争の少ない市場を構築した取り組みについて、3回に分けてお送りします。
第1回は、「サカナバル」誕生の背景や競争の少ない市場戦略、そして六本木への店舗拡大などについてお送りします。
この記事の目次
「サカナバル」展開のきっかけ
株式会社アイロムは、ダイニングバー「BEE8(ビーエイト)」と、恵比寿・六本木・五反田で展開する「サカナバル」を運営しています。また、これらとは別に缶詰工場も手がけています。
私はもともと前職の会社で「ビーエイト」のオープニングに参加していました。しかし、その会社が倒産し、いくつかの事業が分割される形となりました。その際、前の会社が抱えていた多額の未払い金も含め、私の会社が「ビーエイト」を引き継ぐことになりました。
しかし、その未払い金を「ビーエイト」一店舗のみで返済していくのは非常に厳しい状況でした。そのため、早い段階で事業を拡大する必要性を感じ、2年後に「サカナバル」をオープンする決断をしました。
「ビーエイト」は、いわゆるダイニングバーで、かつて流行したグローバルダイニングやケンズダイニングのような、大箱でおしゃれな店をイメージしていただけると分かりやすいと思います。1999年頃、90年代の終わりを感じさせる雰囲気を踏襲した店舗です。

魚バルの業態の飲食店をスタートしたい
以前の会社で、私は魚をメインにした洋風業態を提案したことがありました。当時、魚を楽しめる居酒屋はありましたが、イタリアンやスパニッシュのお店はほとんどありませんでした。そのため、私はこうした新しい業態を実現したいと考え提案したのですが、残念ながら採用されませんでした。
この経験から、私が独立した際には自分の提案が正しかったことを証明したいという強い思いが生まれ、魚バルという魚を中心にした飲食店をいつかスタートさせる決意を固めたのです。
「サカナバル」の一店舗目は、恵比寿の線路沿いにある17坪・約30席という小規模な店からスタートしました。
しかし、先輩方からは「商圏が360度ではなく180度しかないから絶対に売れない」と厳しい意見をいただくこともありました。とはいえ、その立地条件のおかげで家賃を安く抑えることができましたし、恵比寿全体の商圏の大きさも相まって、立地の制約による影響はほとんどありませんでした。
閑散からスタートした「サカナバル」
お店がある恵比寿のエリアは、今でこそ多くの飲食店で賑わっていますが、オープン当初は周辺に飲食店がほとんどないエリアでした。私たちの店にはお客様がほとんど来ませんでしたが、目の前には「亀戸ホルモン」という大繁盛店があり、駅近くまで続く長蛇の列ができていました。私は、従業員と一緒にその列を眺めていたのを覚えています。
しかし、列に並ぶお客様たちが私たちの店にも興味を持ち、「あの店は何だろう?」といった様子でこちらをちらちら見ているのが分かりました。そこで思い切って、列に並んでいるお客様に「一杯だけどうぞ」と声をかけ、ドリンクを振る舞うことにしました。長時間並ぶのは大変だと思うので、少しでも気分転換になれば、との思いからでした。
その結果、この間のお礼という形で少しずつお客様が来店されるようになり、次第に店の雰囲気が賑やかになり始めました。
ニーズに応じたメニューの変化
「サカナバル」を立ち上げる際には、最初にメニュー構成や価格帯を明確に設定しました。当時、イタリアンの平均客単価は約5,000円、居酒屋は約3,000円であったため、この中間の価格帯を狙い、3,000円から5,000円の範囲でメニューを構成しました。そして、価格設定に基づき、盛り合わせや単価の高い料理、手に取りやすいメニューなどをバランスよく組み合わせることにしました。
メニュー構成は、魚を使った料理でさまざまなジャンルに対応できるスタイルを取り入れ、前菜から和食、洋食まで多岐にわたるメニューを展開しすることにしました。例えば、恵比寿店では名物のカルパッチョ盛り合わせを前菜として提供し、その後にアクアパッツァなどの魚料理を続ける流れを採用しています。
また、時代やお客様のニーズに応じてメニューを変化させることも心がけています。例えば、生牡蠣をミキサーにかけてそのままソースとして提供するなど、独自のアプローチを取り入れ、創意工夫を重ねることで新たなメニューが次々と生まれ、独自のスタイルを確立していきました。
「魚」で競合の少ない市場を築く
最初からメニューが受け入れられたわけではありませんでした。よく聞かれたのが「魚介アレルギーなんです」という声です。内心では「店名に魚が入っているのに、調べてから来てほしい」と思うこともありましたが、そういったお客様は少なくありませんでした。
そこで当初は「お肉も用意すべきか」と考え、唐揚げや和牛ほほ肉の赤ワイン煮込みをメニューに追加し他こともあります。しかし、それもほとんど売れず、「一本化した方がいい」と判断し、フィッシュオンリーに切り替えることにしました。それでも最初の3ヶ月間は迷走が続き、毎日のようにメニューを変更していました。
メニューが固まったのは、特定の料理がヒットしたからではなく、「魚」というテーマが受け入れられたためだと思います。当時のヘルシー志向の流行に乗れたことで、女性客を惹きつけ、来店が増えたことが成長に繋がったのです。
お肉は効率的でロスが少ないのですが、魚は腐りやすく、技術も必要なため、真似されにくいという特徴もあります。魚を選んだ理由は競合が少ないからであり、魚に特化することで他店との差別化となり、競合の少ない市場を築けると考えています。魚を中心に据えた挑戦は、他店との差別化に繋がり、競合の少ない市場を築けると信じています。
条件不利な六本木への挑戦
恵比寿の店舗が成功し、その約2年後に次のステップとして六本木への出店を決めました。六本木の店舗は飲食店街から少し離れた場所にありましたが、当時の勢いを背景に、その場所で挑戦することを決意しました。
もともとその場所にはうどん屋さんが営業していましたが、一度立ち退いてマンションが建設され、その後に再び戻ってきました。しかし、立地が以前と大きく変わった影響で売上が伸びず、半年ほどで「もう撤退したい」という話になったそうです。そのタイミングで物件のオーナーからメーカーを通じて私のもとに話が持ち込まれました。
多くの飲食店経営者が「やりたくない」と敬遠する中、私は現地を確認し、「これは行けるかもしれない」と直感しました。その場所は歩道から約10メートル奥に入った目立たない立地であり、スーパーのように目的地であればお客様が来る可能性はあるものの、飲食店としては非常に難しい立地と見られていました。それでも、当時の勢いと自信があったことから、「挑戦してみよう」と決断しました。

目的来店を実現する六本木での戦略
六本木の物件に価値を見出せた理由は、恵比寿での成功体験が大きかったと思います。夜10時を過ぎると「1分間裸で歩いても誰にも気づかれないのでは」と感じるほど人通りがなかった恵比寿に比べると、六本木の条件はまだ良いと感じました。
六本木も悪条件ではありましたが、「目的来店」を実現できれば十分に勝算があると考えました。そのため、SNSを徹底的に活用し、話題作りに力を注ぎました。とはいえ、恵比寿のお客様がそのまま六本木に来てくれるわけではないため、新たな話題作りが必要でした。オープン前には、ロケーションの悪さをどうカバーし、売上を上げていくかを試行錯誤しました。
私は前職でも店舗の立ち上げを経験していたため、広告手法を模索することには慣れていましたので、まずはSNSを最大限活用すると同時に、ポスティングや中吊り広告にも挑戦しました。中吊り広告では、ロゴだけのデザインに70万円以上をかけましたが、正直なところ全く反応がありませんでした。身内ですら広告に気づかなかったほどで、その時は「やりすぎた」と反省しました。それでも、試行錯誤を繰り返す中で、徐々に方向性が見えてきたと感じています。
第1回は、「サカナバル」誕生の背景や競争の少ない市場戦略、そして六本木への店舗拡大などについてお送りしました。
第2回は、立地条件やマーケティング手法、広告やSNSを活用した集客戦略、そして週末、年末の経営戦略などについてお送りします。