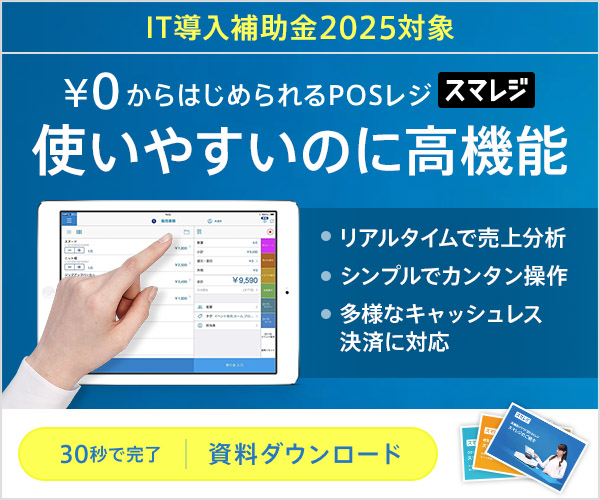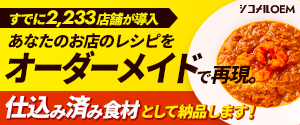about![]()
「お店ラジオ2」は、店舗経営にまつわるトークラジオ番組です。小売店や飲食店など各業界で活躍するゲストをお招きし、インタビュー形式でお届けしています。この記事は、InterFM・FM大阪で毎週日曜日にお送りしている「お店ラジオ2」で放送された内容を再編集したものです。
今回のゲストは、「ラーメンを“消去法”で選び、ゼロからミシュラン常連店を築き上げた男」―株式会社イノセンス 代表取締役 水原裕満さんです。元バンドマンからスタートし、現在は複数ブランドを展開。再現性と持続可能性を軸に“イケてるラーメン屋”を追求するその歩みに迫ります。
ラーメン職人として異色の経歴を持つ水原さんが、飲食業界に足を踏み入れた経緯から、株式会社イノセンスを創業し、ミシュラン常連店を複数手がけるまでの軌跡、そして再現性と持続可能性を軸にブランド設計・多店舗展開を進める経営哲学について、3回に分けてお送りします。
第1回は、元バンドマンの水原さんが飲食の道を選び、ラーメン店を開業するまでの経緯や、ゼロから味を築いた創業初期の苦労についてお送りしました。
第2回は、「らぁめん小池」から始まった店舗展開と、各ブランドの戦略、再現性と持続可能性を意識したレシピ設計などについてお送りします。
この記事の目次
“人目につく場所”への挑戦と立地の難しさ
よく「住宅街と駅近では戦い方が全く違う」と言われますが、実際、その違いは運営に大きく影響することを実感しています。駅近の物件は家賃が高く、その分回転率を上げる必要があり、営業時間も長くなります。結果として、スタッフのシフト管理も複雑になりがちです。
現在の私たちは、「とにかく数を売る」フェーズではなく、「人目につく場所に出店する」フェーズに移行しています。そうした考えのもと、次の一手として出店したのが、本郷に構えた「本郷苑」でした。
この物件は大通り沿いにあるものの、入口が奥まっており視認性が悪いため、オープン当初は思うように売上が伸びませんでした。近くにある「中華蕎麦にし乃」が好調だったこともあり、「同じ通りならば、にし乃と同程度の集客が見込めるのでは」と考えましたが、現実はそう簡単ではありませんでした。
あらためて、店舗の“間口”や視認性の重要性を痛感しています。それでも最近では、昼時には行列ができるようになってきており、少しずつ手応えを感じ始めています。

流行より“定番” 持続可能なブランド設計
私が手がける「らぁめん小池」「中華蕎麦にし乃」「キング製麺」「つけめん金龍」は、すべて自分でレシピを考えています。そのため“手グセ”が出てしまい、「なんとなく似ている」と気づかれることもあります。
とはいえ、屋号ごとにコンセプトを変えているため、それぞれが独立したブランドとして成立していると考えています。たとえば「つけめん金龍」は、ベースのスープは「にし乃」とほぼ同じですが、自家製麺によって“麺の美味しさ”を引き立て、まったく違った印象になります。
ラーメン業界は流行の移り変わりが激しく、毎月のように新たなスタイルが登場しますが、私は“定番”として残るラーメンを意識して作っています。流行を追いすぎると、お店の寿命が短くなると感じているからです。
「つけめん金龍」は2021年にオープンした7席だけの小さな店で、やや尖ったコンセプトでしたが、だからこそ挑戦できました。家賃や人件費を抑えた分、味に集中できたのが強みです。ミシュランガイドにも掲載され、反響により売上は1.2〜1.3倍に増え、認知度も着実に広がっています。
新しいメニューへの挑戦〜チャーハン〜
本郷の店舗では、ラーメンだけでなくチャーハンにも力を入れています。その背景には、厨房設備をしっかり整えることができたことがあり、新たなメニューにも挑戦してみようと考えたためです。
ちょうどその頃、自動でご飯を攪拌できるチャーハン専用の調理機に出会ったことも、大きなきっかけの一つでした。この機械は非常に便利で、職人に負担をかけず、味のブレも少ないのが特長です。油や卵、塩の分量も細かく設定でき、常に安定した仕上がりが得られます。鍋が汚れるのを避けるため醤油は使わず、塩コショウで味を整え、連続調理が可能な工夫も施しています。
チャーハン自体はシンプルで差別化が難しい料理ですが、トッピングで個性を演出しています。「エビチャーハン」や「唐揚げタルタルチャーハン」など、具材にバリエーションを持たせ、SNSでも積極的に発信しています。
新しいメニューへの挑戦〜家系ラーメン〜
実は「らぁめん小池」で現場に立っていた頃、夜限定・週末限定で家系ラーメンを提供していた時期があり、それがかなり好評でした。家系ラーメンには熱狂的なファンが多く、ビジネスとしても強いジャンルだと感じています。私自身も家系ラーメンを食べて育った世代なので、新しい店舗を出す際に「やってみようかな」と、ある意味では軽い気持ちで始めた部分もあります。
ただし、家系ラーメンのお客様と「らぁめん小池」のお客様は、全く異なる層です。家系ファンには、1日に2杯食べるような人や、「直系でなければ認めない」というこだわりの強い方も多くいます。とはいえ、そうした熱量のあるお客様がSNSや口コミで話題にしてくれたことが、結果的に店の注目度を高めてくれました。もちろん、盛り上がりすぎると大変なこともありますが、賛否両論が出るくらいがちょうどいいと感じています。
ちなみに現在、すべてのメニュー開発やブランド設計は私ひとりで行っています。毎年のように新しいことに挑戦しているため、正直なところ、そろそろ限界も感じ始めています。知人や周囲に相談しながら進めてはいますが、最終的な判断は常に自分。やはり、そのプレッシャーは大きいです。
イケてるラーメン店をどう作るか
まずは、流行っている店を実際に見に行くことから始めます。行列ができている店には必ず理由があり、それを自分の目で確かめ、分析します。訪れるのは、SNSで話題になっている店だけでなく、地元で静かに人気を集めている店などにも足を運びます。注目するのはメニュー構成や味の方向性です。たとえば最近では、複数のチャーシューを盛りつけたラーメンが増えており、食べる側には楽しい一方で、作る側には負担が大きいメニューも見られます。
私たちの店では、「現場で無理なく再現できるかどうか」を導入判断の基準にしています。たとえ人気があっても、オペレーションが厳しい場合は取り入れません。ただし、将来の参考になりそうなアイデアについては、メモや写真で記録しておくようにしています。
実際のところ、ひとつのメニューを追加するだけでも、多くの時間と試行錯誤が必要です。「何でもできる」と思われがちですが、現場で形にするのは決して簡単ではありません。他店で気になる取り組みがあれば、信頼関係を築いたうえで話を聞くこともあります。まずは何度も通い、自分の想いを伝えることから始めます。距離感や礼儀を大切にし、こちらの本気度や愛情が伝わるよう努めています。

イケてるラーメン屋を作るための方程式
イケてるラーメン店を作るための明確な方程式はありませんが、私なりに意識していることはいくつかあります。まずは、流行っているお店をチェックし、「なぜ美味しそうに見えるのか?」という視点で、SNSや現地で観察するところから始めます。構図や色使い、トッピングの配置など、細部に目を向けて参考にしています。
ラーメンは使える具材が限られているため、盛りつけの工夫が非常に重要です。たとえば、麺を見せたいときは具材を端に寄せ、逆に麺を隠したいときは具材で覆うように配置するなど、印象をコントロールしています。オープン後は、実際のお客様の反応や、自分の感覚をもとに盛りつけを微調整していきます。
とはいえ、それを実現するには技術が必要です。とくに麺の整え方は見た目以上に難しく、現在は社員のみが担当するようにしています。
また、私たちの店舗は基本的にオープンキッチンを採用しており、お客様の目の前で調理を行います。オープンキッチンでは教育中の様子が見えないようにするなど、やり直しの少ない体制が求められます。そのため、一部の店舗では視線をやわらげる設計も取り入れています。
立地に応じて、店づくりの方向性も変えています。たとえば新宿のような繁華街では、“シズル感”はあえて抑え、器の美しさで魅せるスタイルにしています。一方で、住宅街やオフィス街では、丁寧な調理の様子をあえて見せることで、安心感につなげています。
最初に出店した「らぁめん小池」「中華蕎麦にし乃」「キング製麺」も、いずれも住宅街にあり、“手作り感”を伝えるような設計を意識していました。最近では、スタッフの技術レベルも踏まえながら、視線のコントロールを含めた店づくりの方向性を少しずつ見直しています。
第2回は、「らぁめん小池」から始まった店舗展開と、各ブランドの戦略、再現性と持続可能性を意識したレシピ設計などについてお送りしました。
第3回は、SNS戦略や人材育成、女性が入りやすい店づくりの工夫、そして今後の多店舗展開とブランドの未来についてお送りします。