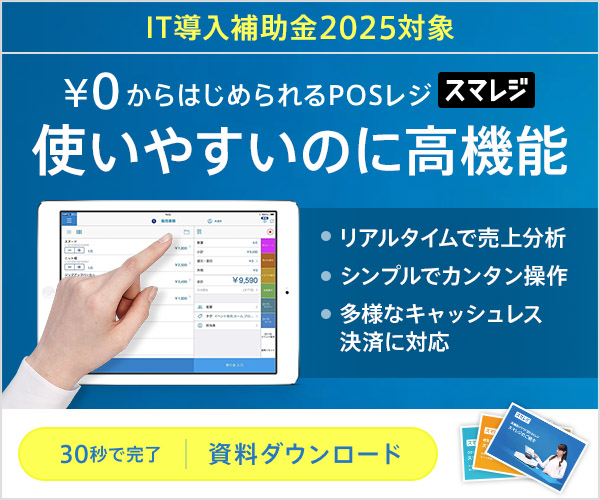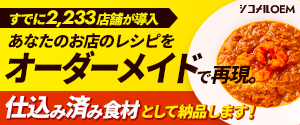about![]()
「お店ラジオ」は、店舗経営にまつわるトークラジオ番組です。小売店や飲食店など各業界で活躍するゲストをお招きし、インタビュー形式でお届けしています。この記事は、InterFMで毎週日曜日にお送りしている「お店ラジオ」で放送された内容を再編集したものです。
今回のゲストは、株式会社アイロム 代表取締役社長兼CEOの森山佳和さんです。ダイニングバー「ビーエイト」や魚料理専門の「サカナバル」を展開。また、缶詰工場の運営にも取り組むなど、飲食業界で独自の挑戦を続けています。森山さんの手がける事業の背景やこだわりについて伺います。
魚をテーマにした新業態の開発からスタートし、飲食店『サカナバル』を展開するに至った背景、恵比寿や六本木といった多様なエリアで成功を収めた戦略、さらに仕入れや経営の改善を通じて競争の少ない市場を構築した取り組みについて、3回に分けてお送りします。
第1回は、「サカナバル」誕生の背景や競争の少ない市場戦略、そして六本木への店舗拡大などについてお送りしました。
第2回は、立地条件やマーケティング手法、広告やSNSを活用した集客戦略、そして週末、年末の経営戦略などについてお送りします。
この記事の目次
雑誌映えする内装で取材を増やす
六本木店のポスティングには高級感のある紙を使用し、内容も細部にまでこだわりました。例えば、グランドオープンの際のドリンク半額サービスでは、「お会計半額」と書くよりも、「どれを頼んでも半額」という表現の方が訴求力は強いと考え、「全品50%オフ」というフレーズを採用するなどしました。
しかし、ポスティングによって大量のお客様が来たわけではなく、最初に効果を感じたのは雑誌の取材でした。オープン前後の2~3週間にわたり、プレスリリースを続けたことが雑誌の目に留まるきっかけになったのだと思います。
雑誌に取り上げられたのは、恵比寿と六本木で内装のコンセプトを大きく変えたからだと思います。
恵比寿では、サンセバスチャンの街並みに溶け込むような内装を目指しましたが、六本木ではまったく異なるアプローチを採用しました。七メートルの天井高を活かし、ロサンゼルスのダウンタウンやオフィス街の角にあるレストランをイメージして内装をデザインしたのです。この内装が雑誌映えする要素となり、取材が決まったのだと思います。六本木の店舗は特に見映えが良かったようで、「東京カレンダー」には何度も掲載され、その後の集客にも繋がりました。
「ムール貝」を使った戦略的なプレスリリース
プレスリリースについては、業者に依頼するだけでなく、自分たちでも行いました。自分たちで発信する場合には、切り口を工夫すれば、何度でも情報を発信することができるため、内容をどのように作り込むかが重要になります。最初はグランドオープンのお知らせのプレスリリースでしたが、その後は話題性のあるフックを作りながら情報を発信していきました。
例えば、国産の生ムール貝を使った「食べ放題キャンペーン」を企画し、それをプレスリリースしたりもしました。当時、ムール貝は繁殖力が強く、牡蠣などに付着してしまうことから「嫌われ者」と見なされがちで、一般的には注目されることが少ない食材でした。しかし、ムール貝の養殖を始めた方のおかげで、冷凍ではない新鮮な国産ムール貝を仕入れることが可能になり、これを食べ放題の形で提供しました。
このキャンペーンは大きな話題を呼びました。フランスでは高級食材とされるムール貝ですが、日本では馴染みが薄いというギャップをうまく活用し、「新鮮で国産」という付加価値を強調することで、多くの注目を集めることができたのです。
ムール貝を使った食べ放題キャンペーンをプレスリリースで発信した際、今で言うインフルエンサーのような存在の方々がブログなどで取り上げてくれたことも注目を集めることができた要因でした。当時はブログが盛んで、それにより感度の高い方々が来店され、紹介してくれるようになりました。飲食業界では受け身で待つ姿勢が一般的ですが、私たちは思いついた企画を積極的に発信し続けることで、徐々にお客様を増やしていくことができたのです。

リピート率を上げることが成功への鍵
「サカナバル」という業態は日常的な食事というより、特別な楽しみとして捉えられることが多く、リピート頻度を上げるには、まずお客様の母数を増やす必要があります。「サカナバル」を選んでくれるお客様の分母は決して多くはないため、分母の拡大が課題だと考えています。
分母を拡大するためには、お客様の日常的な生活サイクルに入り込むことが重要で、私たちは「ファン」の獲得に努めています。誰にでもリピートされる店を目指すのではなく、特定の層にしっかりと刺さるアプローチにより、大切なファンを一人ずつ丁寧に増やしていくことが、成功への鍵だと確信しています。
私たちの戦略は、特定の層で強く支持してくれるお客様を見つけることに重点を置いています。百を投げて一が返ってきたら、その一を大切にしながら、次の百を探すという地道な努力を繰り返しています。
予想外の団体利用の増加
「サカナバル」を運営して意外だったのは、団体客の利用が多い点です。幹事の方が選んでくださることが多く、宴会需要があることに気づきました。この業態は年配の方々にも好まれており、12月の忘年会シーズンには「焼肉」や「居酒屋」といった定番の選択肢の合間に「少し変わり種」として選ばれることが多い傾向があります。
当初は魚をメインにした業態のため、宴会需要は少ないだろうと考え、宴会コースを用意していませんでしたが、実際には一定の需要があることが分かり、メニューを作りました。洋食魚が好きな方ばかりでなく、「いろいろな料理が楽しめる」という理由で選んでくださることも多いようです。特に五反田の店舗では、牡蠣やハマグリ、つぶ貝、サザエなど、貝を専門に扱った「貝尽くし」のメニューがあります。
また、価格帯が5,000円以内で楽しめる点も宴会需要を高める理由の一つだと思います。忘年会をきっかけに来店された幹事の方や数名のお客様がリピーターとなり、周年イベントなどにも訪れてくださることが増えています。このように、地道な努力が確実に成果を生んでいると感じています。
金曜日の緊張感にワクワクする
私は、お店の安定した経営には、団体客の取り込みと特に週末の売上を最大化することが必要だと考えています。特に金曜日の売上にこだわり、そのピークをどれだけ高められるかを重視しています。金曜日の営業では最新の注意を払い、お客様を初めての回転のように迎えるよう心がけています。
特に12月は1年で最も売上が伸びるトップピークの時期ですので、この期間の売上を高めることが重要であり、スタッフにはピーク時の質を高めるよう伝えています。
私自身は、金曜日の緊張感には独特の楽しさを感じていて、金曜日の予約がたくさん入っているときにはワクワクしてしまいます。「今日は何かしらのトラブルが起きるかもしれない」と思いながらも、それをチームで乗り切ることに喜びを感じます。そのため、「みんなでボールを拾う」という意識を常に持ち、助け合いながら業務を進めることをスタッフに繰り返し伝えるようにしています。12月のピーク時期を全力で乗り越え、新たな1年を迎えるという感覚で、準備を怠らないことよう心がけていました。
清潔な状態ですべてのお客様を迎える
恵比寿の店舗では1月から12月まで安定した売上が続き、毎日がトップピークのような状況でした。このような環境では、細部に気を配ることが非常に重要です。例えば、汚れたメニューはお客様の気持ちを冷めさせる原因になります。そのため、お客様には清潔なメニューを提供するよう徹底していました。
時には気が緩み、汚れたメニューや曲がったものがそのまま出されることもありました。そうした場合には強く指導し、スタッフ全員の意識を高めるよう努めていました。この意識は時間の経過と共に薄れがちになるため、繰り返し指導することが欠かせません。
特に金曜日や12月のようなピーク時期は、意識を再確認し、全員で気を引き締める絶好の機会だと考えていました。これをチーム全体で共有し、改善と成長を続けることを目標にしていました。

ターゲットの設定
恵比寿から六本木へと店舗を展開し、次に五反田で貝専門という、さらにニッチな専門店を開業することにしたのです。オイスターバーではなく、貝全般を扱うことにした理由は、コアな貝好きのファン層を狙うためでした。貝好きは鮮度や種類に詳しく、その要求に応えることは私たちの得意分野であると考えたのです。
店舗はビルの5階に位置する空中店舗であり、目的来店型の戦略を取る必要がありました。このため、私たちは業態をさらに尖らせ、明確なターゲットを設定することにしました。貝専門店の客層は他店舗と異なりますし、恵比寿や六本木で展開していた頃から、それぞれの店舗で客層が違い、特にコロナ禍では店舗を縮小する中でメニューや内装、食材を大きく変えていましたので、「サカナバル」という名前を残しつつ、店舗ごとに全く違う業態のようなスタイルになっていました。
空中店舗には焼肉屋や寿司屋などが、それが成功しているのは、「目的来店型」という強みがあるからです。「焼肉を食べに行こう」という明確な動機づけが強い点が、その成功の鍵となっています。
第2回は、立地条件やマーケティング手法、広告やSNSを活用した集客戦略、そして週末、年末の経営戦略などについてお送りしました。
第3回は、仕入れ改革と魚料理の可能性、そして大きな分母とコアファンの獲得などについてお送りします。