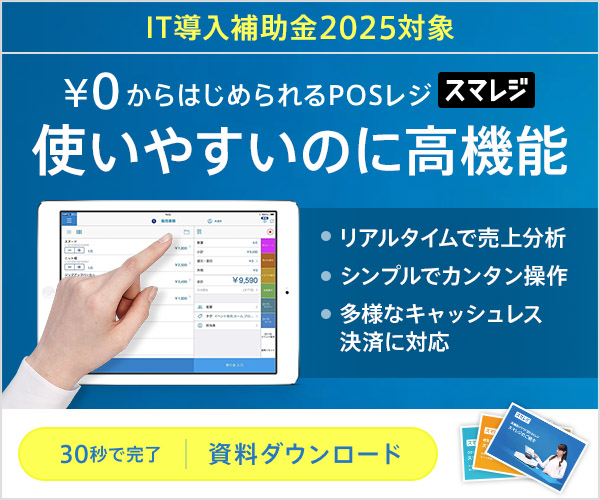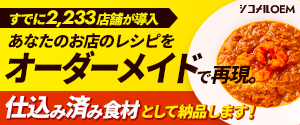about![]()
「お店ラジオ」は、店舗経営にまつわるトークラジオ番組です。小売店や飲食店など各業界で活躍するゲストをお招きし、インタビュー形式でお届けしています。この記事は、InterFM・FM大阪で毎週日曜日にお送りしている「お店ラジオ」で放送された内容を再編集したものです。
今回のゲストは、漢方職人であった祖父の技術を受け継ぎ、クラフトコーラ専門メーカー「伊良コーラ株式会社」を創業した代表取締役/コーラ職人の小林隆英さんです。独自の製法で作られる「伊良コーラ」は、伝統と革新を融合させ、和牛や高級バーなど、こだわりの場面で愛されている一品です。
祖父から受け継いだ漢方技術をもとにクラフトコーラ「伊良コーラ株式会社」を創業し、伝統と革新を融合させたユニークなコーラを作り出すまでの経緯、そしてその商品がどのようにして特定のシーンで強く共感されるようになった背景や、今後の展開について、3回に分けてお送りします。
第1回は、クラフトコーラとの出会い、クラフトコーラのコンセプト、「伊良コーラ」の誕生などについてお送りしました。
第2回は、新しくおしゃれなクラフトコーラと創業の経緯、キッチンカー・シロップ・オンラインストアーの展開などについてお送りしました。
第3回は、店舗のオープン、缶コーラの誕生とローソンでの販売、組織の課題と今後の展開などについてお送りします。
この記事の目次
伊良コーラ総本店 下落合のオープン
メディアに取り上げられ、ECサイトで売れるようになった頃には、月商が100万円を超えていたと思います。しかし、伊良コーラは小ロット生産のため、原材料費が高くなっていました。それでも、当時は私一人で運営していたため、人件費や販売費がほとんどかからず、利益を出すことができていました。
しかし、固定の店舗がなかったため、「どこで作っているのかわからない」や「OEMで作っているのか?」といった声を聞くようになりました。自分では、こだわりを持って自社で製造していることを発信しているつもりでしたが、全く伝わっていなかったことに気付いたのです。
そこで、製造過程が見えるように、工房の横に小さな直売所を作ることにしました。ガラス張りにして、誰でも製造の様子を見られるようにし、2020年2月、工房の隣に「伊良コーラ総本店 下落合」をオープンしました。その結果、店の前には数百メートルもの行列ができ、知り合いから「電車からでも行列が見えたよ」と言われるほどの盛況となりました。
RTD(缶商品)での成功と売り上げの停滞
その後、2020年の夏に、高島屋さんから「シロップではなく、すぐに飲める商品をお中元にしたい」という依頼をいただきました。ちょうどその頃、缶を開けてすぐに飲めるRTD(Ready to Drink)商品を作りたいと考えていたのですが、充填会社への発注ロットが1万本と大きく、当時の小規模な事業ではその在庫を抱えるのが怖く、なかなか踏み出せない状況でした。
しかし、高島屋さんが8,000本ほどをお中元用に引き取ってくれると約束してくれたため、「これならできる」と思い、挑戦することにしました。RTD商品が完成し営業をかけたところ、予想以上に反応が良く、2020年の夏まで順調に売れていきました。
しかし、2021年に渋谷店を出店したことが大きな転機となりました。当時は3〜4人の少人数で、メーカー業務と下落合の店舗運営を同時に行っていましたが、渋谷店の出店によってオペレーションや製品開発がうまく回らなくなってしまったのです。
その結果、より良い商品を開発するための時間やリソースが不足しました。さらに、2021年にはクラフトコーラメーカーが急増し、大手企業も市場に参入してきました。私は渋谷店の運営に追われ、成長の波に乗り切れず、売り上げも停滞してしまいました。
缶のクラフトコーラを作り、世の中に広めたい
私は「缶のクラフトコーラを作り、世の中に広めたい」という思いを強く持っていました。当時、クラフトビールは瓶から缶へと移行しており、知り合いのクラフトビールメーカーも缶商品で大きく市場を拡大していました。
しかし、ノンアルコールのクラフト飲料を缶で提供しているところはほとんどありませんでした。
缶にすることでクラフト感が損なわれるのではないかという不安もありましたが、2022年4月から缶の研究を始めました。しかし、瓶から缶への移行は非常に難しく、さらなる研究が必要でした。
その理由は大きく二つあります。まず、これまでの製法ではレモンやライムの皮、スパイスの粒などが多く含まれていました。
しかし、缶の場合、高速で充填する際にこれらの粒が充填機に詰まってしまうという問題が発生しました。従来の技術では対応できなかったため、美味しさを保ちながら新しい技術を開発する必要がありました。
もう一つの課題は、缶の充填を請け負ってくれる会社を見つけることの難しさでした。資金や人員が不足していたため、自社で工場を立ち上げることができず、大企業に依頼するしかありませんでしたが、なかなか引き受けてもらうことができませんでした。

「応援したい」と言われ、ローソンで販売
缶の商品の開発にあたっては、クラフトビール業界の方々やバーテンダー、さらにはラーメン屋さんや焼肉屋さんにもヒアリングを行いました。そして最終的に、粒をなくしても香り高く仕上げる製法を開発し、この問題を解決することができました。
充填に関しては、飲食業界にいた高校時代の同級生に相談していたところ、その会社の役員の方と繋がることでき、直接お願いしたところ「応援したい」と快く引き受けていただけました。
当初、発注ロットは最低10万本が基準でしたが、数万本まで減らしてもらい、まずはナチュラルローソンさんで先行発売を行うことができました。その後、一般販売やオンラインでの展開も開始し、3〜4ヶ月で売り切れると予想していた商品は、わずか2週間で完売しました。
また、コンビニでの販売について、それまでのお客様からネガティブな反応があるのではないかと心配していましたが、逆に「コンビニでも買える」ということで、喜んでくださいました。
瓶やシロップを好むお客様も引き続きいらっしゃって、商品のバランスがうまく取れていたと思います。
スタートアップ企業に必要な体制
コンビニで缶が販売され、「儲かっているだろう」と言われることが多いですが、実際には経営に余裕があるわけではありません。現在、コアメンバーは4〜5人で、経営判断は私一人で行っていますが、スタッフが定着せず、入っては辞めるという状況が続いています。
「小林さんはブランドやプロダクトを作る才能はあるかもしれないけど、リーダーには向いていないのではないか」と指摘されたこともあります。
和製スティーブ・ジョブズと呼ばれることもありますが、最近では経営者として自分自身が変わらなければならないと強く感じています。特に、組織運営については他のスタートアップでもよく話題になるように、組織論が非常に重要だと考えており、これが最近の大きな悩みの一つです。
一般的にスタートアップでは、ナンバー2を見つけることが重要だと言われます。社内をまとめるリーダー役がいて、社長が旗振り役として研究職に専念できるような体制を作ることが大切だと思っています。
お客様との接点を増やすことが重要
今後は、直営店を増やしたいと考えています。現在はキッチンカー、渋谷店、そして工房がありますが、将来的には都内に10店舗ほど展開したいと思っています。
カフェスタイルの「コーラスタンド」のような形を考えており、業態としてはタピオカ店に近い形になると思います。
出店エリアについてはまだ具体的な物件を見てはいませんが、上野、浅草、秋葉原などに興味を持っています。さらに、海外展開も視野に入れており、現在は台湾やオーストラリアでのフランチャイズ展開の話も進んでいます。
また、コラボレーションにも力を入れています。最近では、神保町に本店があるグリッチコーヒーさんとコラボし、コーヒーとコーラを組み合わせたメニューを提供しました。
このコラボは、台湾でのイベントがきっかけで、グリッチコーヒーさんの代表の方と出会い、そのインスピレーションを受けて実現したものです。私たちは、様々な場所に出店し、お客様との接点を増やすことで口コミが広がり、ファンが増えていくことが重要だと考えています。
さらに、フランチャイズ展開にも非常に興味があります。コーラのビジネスモデルとしては、シロップを現地に送り、現地で炭酸を準備してボトリングするという方法が最も効率的で、このモデルはフランチャイズに非常に適していると考えています。